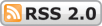|
2種類の森
昨日に引き続き、今日も川上村からです。
朝起きると、結構な雨が降っていました。日本一降水量の多い大台ケ原の隣ですから、雨が多くて当然なのですが…。当然山々には杉が植わっているわけで、花粉症の私にはこの時期にあまり来たくない場所です。1~2週間予定が早かったら、来るのを断念してたかもしれません。山の中に入っても普段とあまり変わらず、正直助かりました。
宿舎を出て、「森と水の源流館」へ行きました。昨日からお付き合いいただいている辻谷館長さんと尾上事務局次長さんが案内して下さいました。
森のジオラマとパノラマスクリーンで森や水の活き活きとした姿を見ることができました。他にも川上村の民家を復元した展示がされていました。
一般の展示を見させていただいた後、辻谷さんと尾上さんから、「和歌山市民の森~今後の方針」についてお話して下さいました。今後必要なのは持続可能な取り組みの工夫と、より多くの様々な属性の方が参加してもらう方法を見出すことのようです。
これまでの活動の中に、川上村から出前講座で来てくれて、森と水の話をして下さるというのがあります。この出前講座を入り口にして、次は実際川上村に来てもらい、本物を体験してもらうことでより理解を深めてもらうという狙いがあります。
そんな森のことを知る話の中で、辻谷さんから「森には2種類ある」というお話を伺いました。1つは原生林、もう一つは人工林で、原生林は決して人間の手を入れてはならない。人工林は必ず人の手を入れなければならない。同じ森でも反対の性質を持っています。人工林に手を入れなければ、地面に日が当たらず、やがては枯れてしまいます。世の中ではしきりに「木を切ってはならない」と叫ばれていますが、切らなければならない木もあるということを教えて下さいました。
昨日も触れましたが、ちゃんと木を育てるために間引かなくてはなりません。その時に間伐材が出てきます。それを割り箸にして使ってやるのか、丸太のままほったらかしにしておくのかで、全然違います。同じ生きてきた木ならば生かしてやりたいというのが、林業に関わる皆さんの気持ちです。
川上村を後にし、和歌山へ戻ってきて、夜には岸本周平後援会西和地区の集会があり、お手伝いしてきました。
|
| |
|
間伐材の活用法を求む!
森林環境保全促進和歌山市議会議員連盟の出張で、和歌山市民の森がある奈良県川上村へ、今日と明日の2日間、視察に来ています。和歌山市からバスで約2時間半、三重県との境に川上村はあります。
まずは川上村役場を表敬訪問しました。川上村は地方財政健全化法による健全化判断では、全国でも5本の指に入る好成績だったそうです。却って和歌山市は後ろから数番目。まさに上流と下流ですねとお話しました。
現在、和歌山市民の森へと続く道が土砂崩れによって寸断されています。次はその現場を視察に行きました。山から道路上に崩れた土砂はすでに撤去されていましたが、ひび割れがあり、いつ再び崩れてもおかしくない状況だということで、通行止めになっています。復旧の目途は立っていません。山へ入って行けないので、市民の森がどういう状態になっているのか、把握できないそうです。
写真はその土砂崩れの現場を背にして撮ったものです。危ないのであまり下に行かないでくれと言われました。
視察の前後をマイクロバスで移動しているときは雪が散らついていました。山々の頂上も少しガスがかっていました。やっぱり市内よりだいぶ寒かったです。
その後、「山幸彦のもくもく館(川上村林業資料館)」へ伺いました。ここには川上村での林業の歴史や使用する道具が展示されており、吉野杉の製材の種類などを知ることができました。
それから村役場の総務課長さんや市民の森を管理して下さっている皆さんと意見交換をしました。その中で出てきたのは、外国からの輸入材に押されて国産の木材が売れない。割り箸でさえも輸入がほとんど。この状態がこのまま続けば、日本の森が維持できなくなってしまう。木を育てるために山を手入れし間伐するが、その間伐材をそのまま山に放ってある。あまりにももったいないので、何か使い道がないかというお話が出ました。
色々と加工してベンチなどに、というアイデアも出ましたが、決定打となるようなものではありませんでした。ぜひ何か良いアイデアがあれば教えて下さい。
|
| |
|
2月定例議会最終日
今議会の最終日となりました。これまで各委員会で審議された議案の可否を全議員で決めます。
各委員長から委員会での審議の報告があり、その報告に対して2人から反対討論がありました。
採決の結果、全ての議案が可決されました。
夜にはよさこい祭りスタッフ部会で、4月5日に行われる春祭りの準備をしました。
|
| |
|
神奈川県受動喫煙防止条例 成立!
今日の神奈川県議会本会議で、松沢成文知事が提案していた「公共的施設における受動喫煙防止条例」が賛成多数で可決・成立しました。来年4月から施行されることになります。
この条例については、関係する各方面からかなりの反対があったようです。当初は屋内全面禁煙の条例でしたが、小規模な飲食店や宿泊施設などは喫煙制限を努力義務とするなど、マスコミではトーンダウンしたとの批判もあるようです。
先日の全国禁煙推進地方議員連絡会の席上で、知事ご本人もおっしゃっておられましたが、10を急ぐあまり0にしてしまっては元も子もないわけで、スタートとしては上出来ではないかと思います。改正を重ねて10にしていければと思います。
和歌山県は全国で初めて教育施設内での全面禁煙を実施しました。神奈川の受動喫煙防止条例をまねて、神奈川の条例にプラスアルファーした条例を和歌山県でやってもらえたらなぁと思います。
今日の和歌山市議会は、明日の最終日に向けて調整のため休会です。だからといって何もしていないわけではなく、クラブ総会を開いてそれぞれの委員会での審議について報告をし、引っかかるところがないか確認をして議案に対する賛否の意思確認をしたり、幹事長会や議会運営委員会が行われました。
|
| |
|
飛行機事故に思う
今朝、成田空港で貨物機が着陸に失敗し炎上。乗員2人が亡くなりました。ご冥福をお祈りします。
昨日、東京から帰ってくるときも強風で飛行機が1時間遅れました。関空へ降りるときも着地したと思ったらものすごく左右に振られて、ヤバいと思ったのですが大丈夫でした。空の上で揺れるより着地したときに振られるのが一番怖いと思いました。
今日の議会は環境保全対策特別委員会が行われました。主には平成21年度から実行される第2次和歌山市環境計画や和歌山市地球温暖化防止計画、環境マネジメントシステムの見直しについて市当局から報告がされ、委員から質疑が行われました。
私は以前から和歌山市がISO14001を取得していることに対して、お金を払ってまで取得する必要があるのか、NPOなどでもっと和歌山市に合ったやり方を提案してくれるところはいくらでもあると思うが、と指摘していました。
今回ISO一辺倒の方向から少し転換した感じになりましたが、しかし計画は庁内だけで策定し、実施したことに対する監査を外部の専門家にやってもらうことにするようです。私としては、やはり計画段階から専門家に入っていただき、しっかりと組んで実施をし、違う専門家や計画した専門家から意見をもらって改善していくというやり方がいいのではないかと思います。
とりあえず、今年1年の動きを見て改善を指摘したいと思いますし、私の知っている環境マネジメントの専門家に一度計画書を見ていただいてご意見を伺おうと思います。
その後は、県連にいたり、書類の整理をしたりしました。党本部と政策についてやり取りもしていました。
人事課から「和歌山県との人事交流について」という文書が届けられましたので、データベースに置いておきます。
|
| |
|
全国禁煙推進地方議員連絡会 結成!
今日、横浜で全国禁煙推進地方議員連絡会の結成総会が行なわれ、参加してきました。
今回、神奈川で行なわれたのは、神奈川県議会に全国で初めての公共的施設受動喫煙防止条例案が提出されたことによります。
会場は満席で多少人があふれてしまうような熱気でした。日テレのカメラも入っていました。しかし、マスコミが1社しかいなかったというのは非常に残念です。
世話人である関口正俊神奈川県議会議員から、会の構成などについて説明がありました。
その後、記念講演ということで、産業医科大学研究員の中田ゆりさんから、現在の禁煙を取り巻く状況や健康被害についてお話を伺いました。日本禁煙学会理事長の作田学さんからWHOなど国際会議での報告を翻訳要約してご報告いただきました。
そして何より、松沢成文神奈川県知事が会場に来られて、今回の条例案を提出するに至った経緯や審議中の思いをお話下さいました。
元々松沢知事は熱のあるお話をされますが、今回は困難な道のりだったのか、一層強く話されていたように思います。今回の条例について、政治家として理想を持って10の政策をしたい。しかし、10を追い求めたために0にしてしまっては元も子もない。政治家である以上は何らかの結果を求められるので、10が理想だけれども、まずは5からでも始めていって、6.7.8と上げていけばいいとおっしゃっておられました。
全国で初めて、教育施設の全面禁煙を実施したのは和歌山県だったのですが、今や禁煙先進県から後進県になってしまいました。神奈川で出来るんですから、和歌山で出来ないはずがないと思うのですが、いかがでしょう。
また会員名簿をいただいたのですが、完全に「西低東高」の状態で、関西のメンバーを増やしていかなくてはならないと思います。ちょっと動かないといけませんね。
|
| |
|
フードアナリストのセミナー
今日は日本フードアナリスト協会主催のブラッシュアップセミナーが行われ、参加してきました。
実は、先月にフードアナリスト4級の試験を受け、なんとか合格しました。この資格は食や食空間を分析し評価するものです。まだまだ駆け出しですので、今日はお勉強です。
講師は4人いらっしゃいました。最初はミホ・シェフ・ショコラティエ代表の斎藤美穂さん。チョコレートに命を賭けるようになったこれまでの経緯をお話して下さいました。斎藤さんのお店のチョコレートは全て手作りされているそうです。余計なものを使わず、本来のチョコレートの味を味わってもらいたいと言うことでこだわっておられるそうです。
参加者にお土産で、ローズエッセンス入りのチョコをいただきました。このローズエッセンスですが、とても手に入りにくいフランス産のバラから作られたもので、1リットル300万円もするそうです。驚きました。
次は日本フードアナリスト協会のスーパーバイザーである藤原浩さんが、フードアナリストとして求められていることをお話下さいました。
その後、キュイジーヌ[s]ミッシェル・トロワグロのヘッドシェフであるリオネル・ベカさんが、主にご自身の作る料理についてお話されました。彼はジャズのような、何度も波のある料理を作るよう心がけているそうです。そんなお話を伺うと、ジャズフレンチをいただいてみたくなりましたが、なかなか手が届かなさそうです。
最後は㈱東京マーケティング代表取締役の加藤秀俊さんです。加藤さんは、フードアナリストとしてどのように表現していくか、具体的な表現技法についてお話して下さいました。
料理や雰囲気、食材の使い方など、それぞれを35文字でまとめていくと、分かりやすく人に伝わりやすいと教えて下さいました。この方法は他にも応用できそうです。
加藤さんはこれから日本版ミシュランのような、レストランの格付け本を企画制作されます。
6時間ビッチリでしたが、とても楽しくためになりました。ありがとうございました。
|
| |
|
戸別訪問
昨日がちょっとハードだったので、今日は9時半過ぎまで寝させていただきました。
それからは、岸本周平後援会西和地区担当の一人として、27日の集会の案内を持って回りました。
始めから分かっていましたが、祝日なのでご在宅のお家が少なかったです。お留守のお家には、名刺に一言書いて、案内をポストに入れさせていただきました。
終わって帰ってきたら17時でした。日が長くなったなぁと改めて実感しました。花粉症もちょっと楽になってきましたし、もうちょっとで終わるのかなぁと期待しています。
|
| |
|
ちぐはぐで落ち着かない日
今日は朝から勉強会に出席するため、東京日帰り出張しました。
病院前から6時53分発の関空リムジンバスに乗るため、10分ぐらい前から待っていました。そこで事件が…。バスが来て、私の前で停まりかけたかと思いきや、そのまま走り去っていきました。大声で「おい!おい!」と叫んだものの届かず。路線バスで和駅まで行って、次のリムジンバスに乗りました。
フライトまで余裕があったから良かったものの、時間を詰めてたらどうしたものかと思いました。私が市内の人間なのでまだ良かったですが、これが外国人や県外からのお客さんだったら、なんと不愉快だったでしょう。月曜にはこのミスの原因と改善策を追求したいと思います。
東京に着いて、虎ノ門にある東京財団へ向かいました。ビルのロビーで開場までの時間を待っていたところ、以前ここでもご紹介した、前佐賀市長の木下敏之先生にお会いしました。13時から「社会のルールについてⅣ 障害と経済について」に参加しました。
障害を負っている方の経済的不利をどのように社会で埋めるか、バリアフリーの実施がどのような経済効果をもたらすのか、というのが勉強会の中身です。主に経済学の学者さんが説明してくれたので、難しくて理解できない部分もありましたが、いただいた論文は何とか理解できる範疇です。
17時半まで続いて、和歌山へとんぼ帰りしました。しかし、帰りの飛行機が15分遅れの出発、20分遅れの到着で、またギリギリリムジンバスに間に合うという状態でした。
本当に、時間に追いまくられる落ち着かない1日でした。
私も読んでいます、木下先生が編集されているメルマガ“夕張市民病院を引継いだ「夕張希望の杜」の毎日”登録フォームはここをクリック
|
| |
|
委員会での採決
昨日までの3日間、委員会で議案の議論を重ねてきました。今日は議案の可否を決める採決が行われました。
採決の前には討論が行われます。討論は、主に議案に反対の場合、どの議案に対してどういう理由で反対なのかを表明するものです。
今回も共産党から、平成21年度当初予算、土地造成事業特別会計予算など、いくつかの予算案に反対の討論がありました。
今回の共産党からの討論でも、その指摘は至極ごもっともなものなのです。しかし、予算案はいくつかのものを一つにまとめて出されているので、その部分だけには反対で他は良くても、賛成か反対のどちらかしか、選ぶことができません。部分反対と言うのがないのです。だから、指摘はごくごく当たり前でも、残った部分を犠牲にできないので仕方なく賛成せざるを得ないことになります。
常々、すごくやりにくいし、おかしいなぁと思っていました。事務局にも聞いてみました。「全体のうちの一部分だけ反対する方法はないのですか?」と。しかし、悪いところも含めて全部賛成するか反対するかしかないと答えてくれました。
その時点で議員は悪いところも含めて容認したことになり、そのリスクを負ったことになります。何かあれば賛成したのだからと、責任を追及されることになります。積極的に賛成した部分については、いくら責任を追及されても構いません。しかし、他を犠牲にしないために制度上仕方なく賛成した部分で責任を追及されたときには、かなりつらいものがあります。
この議会制度がどうにか改善できないのかなぁと思うところです。
19時から、JCの3月度例会とよさこい祭りの実行委員会がありました。私はよさこい祭りのスタッフ担当コーディネーターなので、実行委員会を休むことはできません。なので、JCの例会を休ませていただきました。すいません。重なるとつらいです。
|
| |
|
水道局の審査
今日の委員会は水道局の審査でした。水道局の経営は比較的安定しています。しかし、人口の減少に伴って給水人口も減りつつあり、そんな中で大滝ダムの建設負担金がかなりの重荷になっています。大滝ダムの建設負担金とは、橋下大阪府知事が今声高に叫んでいる「国直轄事業の市町村負担金」です。
かなり前にもお話しましたが、大滝ダムは紀ノ川の上流に建設されています。国土交通省は多目的ダム法という法律を盾に、和歌山市が負担金を払わなければ紀ノ川の利水権を認めないと脅しをかけてきました。利水権がなくなれば、水道が使えなくなって困るのは和歌山市民です。兵糧攻めにしようというのが国交省の魂胆です。
和歌山市には国交省に対して物申すチャンスがあったのですが、はっきりとケンカを売ったのは橋下府知事が先でした。
この建設負担金が今後和歌山市の水道財政を徐々に圧迫していくことになるのではないかという危惧が、委員会の場でも出てきました。
夜には、よさこい祭りのスタッフ部会が行なわれました。4月5日に行なわれるおどるんや春祭りの役割分担を決めました。今年のお祭りにも、一人でも多くのスタッフが集まるようにと思っています。
|
| |
|
定額給付金の実施計画が決まる
今日の議会は委員会審査の2日目です。建設企業委員会では建設局中住宅部と下水道部の審査が行なわれました。
住宅部の審査では、スカイタウンつつじヶ丘造成に係る借金について質問がありました。また市営住宅の空き地を住民が勝手に駐車場にし、管理組合が駐車場代を徴収していたことも改めて質疑に上がりました。全ての駐車場整備が終らないと市が徴収業務にかからないと住民に約束したからということで、すでに整備の終った駐車場でも未だに徴収が始まっていません。
市の歳入に直結するのに、それを見す見す逃していくやり方はおかしいと言う強い指摘がありました。
下水道部の審査で「平成21年度工事概要」が配布されました。また産業部から「直川用地企業進出者の募集について」が届けられました。ともにデータベースに置いておきます。
和歌山市の定額給付金について、実施計画が発表されました。3月31日に必要な書類を発送し、4月1日から受け付け、1回目の給付は4月28日になるそうです。ゴールデンウィークには間に合うように準備してくれているようです。
詳しい内容はPDFにしてデータベースへ置いておきますので、併せてご覧下さい。
|
| |
|
お宅訪問
昨日も少し触れましたが、私は岸本周平後援会西和地区担当の一人です。西和地区の担当は数人いますが、それぞれがある程度同じぐらいの地域を割り振って受け持つ担当制になっています。
3月27日の金曜日に「岸本周平と語る会」を行うのですが、その告知で受け持ちのお宅を回りました。
あえて土曜日のお昼を狙って行ったのですが、ご不在のお宅が多く、どうも当てが外れたようです。
今、自転車を持ち合わせていませんので、歩いて回りました。花粉が気になって、初めのうちはインターホンを押す時にマスクを外して、お話が終わったらまたつけてとしていたのですが、面倒くさくなって、気合も入っていたのか、症状が出なかったので、そのまま外してずっと回りました。
16時半も過ぎて、風も強くなり、雨もぱらついたりで、寒くなってきたので、撤退しました。思っていた件数は回れませんでしたが、まずまずの成果だと思います。
|
| |
|
当初予算案が委員会審査へ
今日はかなりの花粉が飛んでいたようです。ものすごくつらい1日でした。私の顔を見て、「顔が死んでるよ」と言う人もいて、今シーズン最悪の状況だったのではないでしょうか。鼻水・くしゃみ・目のかゆみと、正に三重苦です。
議会では、今日から09年度当初予算案が各委員会に割り振られたのを受け、委員会での審査がスタートしました。私の所属する建設企業委員会では消防局と建設局中基盤整備部の審査が行われました。
当初予算の審議は、全ての分野について大まかではありますが全部説明がありますので、かなりの時間を要します。各委員からの質問も全ての箇所に及び、昨年度との比較など説明を求められますので、必然的にやり取りが多くなります。
そして、2月定例議会の委員会では、3月末で退職される方々からの挨拶があります。消防局では小畑消防局長が挨拶され、ご自身が任を拝命されたときのお母さんとのやり取りをお話され、私の涙腺がゆるくなってしまいました。そのお母さんも局長の退職を見届けないまま、昨年に亡くなられたそうです。基盤整備部では河川港湾課長が挨拶され、途中で感極まっておられました。
春は別れの春であり、またまもなく出会いの春がやってきます。
夜には岸本周平後援会の西和地区会議があり、出席しました。西和地区では3月27日(金)の夜に、岸本周平を囲む集会を予定しています。お手元にご案内が届くかと思いますが、よろしくお願いします。
今日の委員会で建設局から「生活関連事業予算(平成21年度当初)」と「平成21年度入札・契約制度の改正について」の資料が提出されましたので、データベースに置いておきます。
|
| |
|
質疑が行われました
今日の議会では、09年度当初予算の他、提出議案に対する質疑が行われました。
質疑とは、市当局から出された議案に対して、その中身の細かい部分を具体的に聞いたり、周辺のデータを前年分や、場合によっては数年分遡って数字を聞き、その議案が提出されるに至った経緯なども伺うものです。
事実確認や詳細を知ることが中心ですから、出された議案に対して、こうした方がいいんじゃないかと提案することはできません。それは一般質問で行うか、委員会審査の際に言うことになります。
夕方には、県文の前で岸本周平さんが街頭演説をするというので、お手伝いに行きました。ボランティアで来て下さった方数名に加えて、山下・片桐両県議、〆木先生も参加されました。県文のホールで銀座まるかんの創業者である斎藤一人さんの講演会があるということで、そのお客さんを狙ってのビラ配りでした。
周平さんは喉の使いすぎか、声が枯れていて、途中で私がマイクを譲り受け、5分ほどしゃべって山下県議にバトンタッチしたら、最後までしゃべってくれました。
明日から市議会は委員会審査へと移ります。
|
| |
|
特別なことはなかったのですが…
今日の議会は一般質問の最終日で、2名が登壇しました。明日は、現在提出されている09年度当初予算に対する質疑が行われます。
その後はしばらくデスクワークで、政治スクールのアンケート用紙などを作成したり、予算書を読んだりしていました。
|
| |
|
コーディネーター会議
今朝は市駅前で街頭演説を行ないました。先日行なった一般質問のこと、西松建設による小沢代表への献金についてなどをお話させていただきました。
今回の献金問題について、私のような党員にとっては小沢代表の言葉しか拠り所がなく、それを信じるより他に術がありません。ですから、直ちに代表辞任と声高に言うつもりはありません。
しかし、今回のことが国民に、政治に対する不信感を抱かせたことは間違いありません。「小沢が言うんだから信じろ」と言われても、国民にはそれを信じるだけの後ろ盾がありません。その点では国民に対して、「期待してくれているのに、それを損なうような話が出てきて申し訳ない」と謝る必要があるとは思います。
それか、いっそのこと議員辞職までして、「総選挙で禊を受けます」と国民に下駄を預ける方法もあります。
あまり他の政治家の進退についてゴチャゴチャ言わないのが主義ですが、話の流れで少し触れました。
街頭演説が終わった後は議会へ。今日も一般質問が行われました。一般質問も明日までです。本会議が終わった後は建設企業委員会の勉強会がありました。
各部局ごとに提出されている議案について、正副委員長が説明を受けます。なぜかうちの委員会はいつも長時間の勉強会になります。円滑に委員会審査を進めるため、委員さんが引っかかりそうなところを事前に探し、前もって資料を用意していただくなど、対処の打ち合わせも同時に行います。
夜にはよさこい祭りのコーディネーター会議が行われました。早いと思われるかもしれませんが、今から準備しなければ全然間に合いません。これからも週1~2のペースでコーディネーター会議や実行委員会が行われます。
|
| |
|
サンキューの日
今日は3月9日、サンキューの日です。
昨年はよさこい祭りの紀州お祭りプロジェクトでも「ありがとうのまち」をテーマにお祭りをし、5周年記念事業で「ありがとうメッセージ」を行ないました。「ありがとうメッセージ」は普段の生活の中でも、感謝の気持ちを伝えたい人に、はがきで気持ちを伝えようとイベントです。
今日の10時から中央郵便局で、「ありがとうメッセージ」のはがきの発送式が行なわれました。その模様は紀州よさこい祭りのホームページでご覧になれます。
最終的には3,030通の「ありがとうメッセージ」が集まったそうです。早いところではもう今日に届いたところもあるそうです。和歌山にありがとうの気持ちがあふれますように。
今朝は和駅前での街頭演説を行ないました。市議会で行なった一般質問の内容などお話しました。また途中で電池が切れて、地声で引き続きしました。
議会では先週から引き続き、一般質問が行われました。今日も3名が登壇しました。
今日、知人が亡くなったとの連絡をいただきました。29才の女性ですが、交通事故で急に彼岸へ渡ってしまいました。まだまだこれからの人生で、社会にとっても大切な存在だったのに、本当に残念でなりません。ご両親やご家族の悲しみは計り知れないと思います。心からご冥福をお祈りします。
私も先日、ちょっとした事故に遭いました。そのことはここでもご報告しました。今回はたまたま軽症でしたが、一歩間違えればどうなっていたか分かりません。私にとっては、生きていられることに感謝する日にもなりました。
|
| |
|
源氏物語-雅楽の調べ
今日は午後から、市民会館小ホールで行われた和歌山雅楽会の定期演奏会「源氏物語」を鑑賞しました。
こういう日本の伝統芸能に触れる機会は久しぶりですし、大学受験のとき、受験勉強もせず、古典で出てきた源氏物語に惹かれて、原文を買って読んだ記憶もあり、行かせていただきました。
雅楽を生で聞くという機会はほとんどないと思います。初詣などのときに神社で耳にしますが、録音したものをスピーカーから流しているのが多いと思います。
開演前に、いただいたプログラムを拝見しました。曲の説明だけではなく、楽器の説明、ミニ知識なども書かれていて、プログラムだけでも楽しく読むことができました。また開演後も、演者の一人が光源氏に扮してお話されるなど、工夫が凝らされていました。
鳳笙(ほうしょう)や篳篥(ひちりき)の音色をあんなにも堪能できる機会はめったにないと思います。
音だけではなく舞いも披露して下さいました。ひとつは「迦陵頻(かりょうびん)」で、これは4羽の鳥が舞う姿を表しています。もう一つは写真にある「蘇莫者(そまくしゃ)」で、聖徳太子が龍笛を吹いていると山の神がその音色に魅了され、どうしても近くで聞きたいと猿に化けて聖徳太子の前に現れ、笛の音に合わせて踊ったと言う伝説を舞楽にしたそうです。
そういうことも説明して下さり、とても楽しめた時間でした。
|
| |
|
青少年育成の研修会
今朝は、和歌山市と海南市の境の海南市寄りに、お店をオープンされた方がいて、開店のお祝いにお店へ行ってきました。ほんの少しですが、お買い物をして、オーナーさんと立ち話させていただきました。
和歌山へ戻ってきて、12時半から「青少年育成施策推進体制充実強化研修会和歌山県研修会」に参加しました。
お昼ですから、お弁当を出して下さいました。でも、ただのお弁当ではありません。このお弁当は高野山BBS会がやっている「コミュニティランチ和(なごみ)」のお弁当で、その上食材はほとんどが和歌山産のものです。そしてその名も「たまスーパー駅弁」です。
このお弁当をいただきながら、高野山BBS会の大江会長さんのお話を伺いました。大江さんもひきこもりの時期があり、その状況から脱出した経験を生かしてBBSの活動をされています。その一つの手法として行われているのが「コミュニティランチ和」の経営だそうです。
続いて、内閣府の大塚参事官さんから国の青少年施策、特に昨年12月に改定された青少年育成施策大綱や昨日閣議決定されたばかりの青少年総合対策推進法案について説明をしていただきました。
その後は、主にひきこもりの方を社会復帰させる活動をしていらっしゃる佐賀県のNPOスチューデント・サポート・フェイスの松尾事務局長さんから、実際の活動についてお話を伺いました。
それから、青少年育成国民会議の上村副会長さんのご指導の下、これまでの議論を踏まえ、会場を3つに分けてグループ討議をしました。私の居た班に与えられたテーマは「社会の中で、青少年指導者はどんな人がいるのか、それぞれの立場の人がお互い連携が取れているのかどうか」でした。
でしゃばって取りまとめ役と発表係をさせていただきました。皆さんのお話を伺っていると、教員のOBやスポーツ指導者のような方に積極的に関わって欲しいという意見がたくさんありました。また、中小企業の経営者など具体的な技術を持った方に、技術の伝承をしながら育成に携わって欲しいとの意見も多くありました。
年齢的にはギリギリ青少年に入るか抜けるかの30才で、まさに同じような年齢の方のことを話し合いました。こういう青少年に関する議論は初めてで、これを入り口に興味を持っていこうと思います。
|
| |
|
09年2月議会での一般質問全文
今日の質問の議事録を記します。なお、これは原稿ベースで、速報版です。実際の議事録は若干異なることをお含み置きください。正規は後に発行される議事録に拠ります。
《質問》
こんにちは。お疲れさまです。民主クラブの山本忠相です。
私たちのこの和歌山市議会では、おととい、各会派による先輩議員の方々の代表質問が行われておったんですが、そのとき東京の永田町、国会では定額給付金が、関連法案ということで第2次補正予算関連法案が可決をされたということであります。
私たちのこの議会では、定額給付金についてはもうちょっと考えろよということで、再考するということの意見書を出したんですが、物の見事に無視をされたというか、全く気にされていなかったというか、私としてはもう怒るというより笑っちゃうぐらい、ただただあきれているという感じがいたします。
この先、日本の政治はどうなっていくのかということがちょっと心配になってきているところであります。
それでは、議長のお許しをいただきましたので、一般質問をさせていただきます。今回は教育施策、そして子育て施策の2点についてお伺いをさせていただきます。
まずは教育施策についてです。
去る2008年10月14日の平成19年度分の決算特別委員会で質疑をさせていただいた第9款教育費、第2項小学校費、第1目学校管理費、第14節使用料及び賃借料の中にある機械等借上料1億1,941万2,102円について、その中身をただしたところ、当局から「コピー等の借り上げ等も入っているんですが、主にパソコンで、小学校52校に24台ずつ」--確認したところ、正確には研究協力実践校というのがありまして、それが4校それぞれに36台、それ以外の学校には22台で、平均して24台ということだそうですが、「52校に24台ずつと、2分校に5台で、計1,258台のパソコンと、サーバーが52校に1つずつと」、和歌山市の教育情報ネットワークである「『きいねっと』の情報サービスなどの契約」「パソコン本体だけの費用ではなく、ウイルス対策ソフトであるとか、サーバーをメンテナンスするためのシステムであるとか、子供たちの教室に入っているパソコンを制御するシステムであるとか、パソコン以外の部分もあります」と御答弁をいただきました。
そこでお伺いをいたします。
今まで1億2,000万円弱の費用を投入し、今後もその予定だと思いますが、まず、どういうシステムを導入したのか、その意図するところは何か、何を目指そうとしているのか、お答えください。
次に、子育て施策についてです。
昨今の経済不況が家庭にも影を落とし、家計を維持するためにお母さんがパートに出なければならないなど、影響が出てきています。特に子育て中のお母さんにとって、子供が病気になったときなどは、おちおち仕事も手につかないというのが本音であると思います。
実際、子供の看護のために過去1年間に取得した休暇日数は、男性雇用者の約8割でゼロから3日であったのに対し、女性の約2割が6日から10日、約3割が11日以上の休暇を取得していることが労働政策研究・研修機構の調査から明らかとなっております。
また、仕事と家庭の両立が難しいため仕事を辞めた理由の第4位に「子供の病気等でたびたび仕事を休まざるを得ないため」というのが入っております。核家族化が進み、別居の祖父母の手助けも得られないということも背景にあるようですが、和歌山市の場合はこの点まだましなほうかもしれません。
1995年からの国の子育て支援策、エンゼルプランから病児・病後児保育事業が始められ、1999年度までに全国500カ所の設置を目指しておりましたが、実際、1999年度末には約2割の110カ所にとどまりました。2000年度からの新エンゼルプランでは、改めて500市町村での事業実施が目標とされ、2005年時点で598カ所まで拡大をいたしました。しかし、依然としてニーズが高く、2005年からの少子化対策、子ども・子育て応援プランでは1,500カ所にまで拡充されることが目指されております。
そんな中で、病児・病後児保育を含めた子育て支援のために、これまで国の直轄事業で行われてきた緊急サポートネットワーク事業を2009年度から市町村へ移管することを厚生労働省が決めました。昨年11月20日の参議院内閣委員会でもこのことが取り上げられ、半年もたたない先にいきなり廃止するのはいかがなものかと議論がなされ、各市町村で行っているファミリー・サポート・センター事業に再編する前提で、とりあえず2年間の経過措置がとられることとなりました。
本市でもファミリー・サポート・センター事業を既に行っておりますが、まずはこれまでの現状と、新規事業に含まれているファミリー・サポート・センター事業の拡充及びその財源についてお答えください。
また、事業の再編に関して、厚生労働省の対応は余りにも性急というか、拙速の感が否めません。先ほどの国会答弁で厚生労働省の北村彰大臣官房審議官が、「これまでも地方自治体に対しまして、予算要求の内容、ファミリー・サポート・センター事業の再編につきましての具体的な内容、あるいは当該事業の必要性、あるいは再編の趣旨、そういったもろもろのことをお知らせをさせていただきまして、また、来年度以降、病児・病後児預かりなどが、次世代育成支援対策交付金、これを利用してそれぞれの地域で実施されるように文書さらには直接電話により働きかけもしておるところでございます。」と答えられています。
そこで、厚生労働省から本市に対し、どのようなアプローチがあり、どのような説明があったのか。
以上をお伺いして、第1問といたします。
《岩橋市民環境局長 答弁》
子育て施策について2点ございます。
まず1点目、ファミリー・サポート・センター事業の現状についての御質問です。
ファミリー・サポート・センター事業は、和歌山市在住で、子育ての支援をしてほしい人と子育てのお手伝いができる人を会員登録し、互いの信頼と了承の上で一時的にお子さんを預かる会員組織を運営する事業でございます。この事業は、平成14年6月から開始して以来、会員数は増加傾向にあり、平成21年2月末現在の会員数681人、平成20年4月から平成21年2月末までの活動件数は2,326件となってございます。
本市では、子育て支援、男女共生を推進する上でファミリー・サポート・センター事業を重要な施策と位置づけており、今後とも引き続き当事業を推進してまいりたいと考えております。
2点目、ファミリー・サポート・センター事業の拡充とその財源について、また、厚生労働省からのアプローチと説明はあったのかとの御質問です。
国では、病気のお子さんや病後のお子さんの預かり及び緊急時の一時預かり等を行う事業である緊急サポートネットワーク事業を廃止し、平成21年度からは、市町村が実施するファミリー・サポート・センター事業の機能を強化して対応するよう制度の見直しを行うこととしています。本市といたしましては、ファミリー・サポート・センター事業の利用者のニーズを考慮し、平成21年度から、病気のお子さんや病後のお子さんの預かり及び緊急時の一時預かりに対応できるように事業を拡充してまいりたいと考えております。
なお、財源でございますが、新たな事業は、事業費のおよそ2分の1が国の交付金で賄われることとなっております。
また、厚生労働省からは、平成20年9月に、平成21年度から国が行っている緊急サポートネットワーク事業を廃止し、市町村が行うファミリー・サポート・センター事業制度の見直しを行う予定である旨の事務連絡があり、その後、平成21年2月に交付金の算定基準等についての事務連絡がございました。そのほかに、事業に関して国から市に対しての説明会等は開催されてございません。
《樫原教育局長 答弁》
教育施策について、小学校で使用するパソコンのリース費用として、1億2,000万円弱の費用を投入し、今後もその予定だと思うが、どういうシステムを導入したのか、その意図するところは何か、何を目指そうとしているのかとの御質問でございます。
小学校で使用するパソコンにつきましては、インターネットにおける有害サイトなどから児童の安全を守るフィルタリングシステムや、ウイルス対策などのセキュリティーシステムを導入し、また、学習面では、漢字学習や計算などの教材システム及びそれを活用するための手書き機能を持つパソコンシステムを小学校52校に導入したものです。
導入のねらいといたしましては、児童が安全にパソコンシステムを利用できる環境の構築、児童の情報活用能力の育成、学力の向上を目的としております。
目指すところにつきましては、手書き機能を持つパソコンシステムを活用することにより、児童が興味を持って学習し、一人一人が教員の指導のもと自分のペースで学習を行い、学力を向上させたいと考えてございます。
《再質問》
それぞれ御答弁いただきましたので、再質問に入らせていただきます。
まず教育についてです。
パソコン導入の意図、目指すところは、子供たちの学力向上であるということのお答えでした。
本市で導入したシステムは、全国でも一、二を争う進んだシステムだそうです。複数のマスメディアにも取り上げられ、海外での学会にも取り上げられたと聞き及んでおります。
ICT--Iというのはインフォメーション、情報、CはコミュニケーションのC、通信という意味ですね、Tがテクノロジー、技術。情報通信技術をICTというのですが--ICTを使った教育環境を整備する今回の研究は、NEXTプロジェクトと名づけられ、独立行政法人メディア教育開発センターとマイクロソフト株式会社によって進められ、現在、京都の立命館小学校、東京都港区立青山小学校など4校と和歌山市立の52校が参加をしております。
戦後GHQが飢えた日本国民にパンやチョコレートを配り、そのときの子供が大人になって、食卓が和食から洋食に侵食されたように、どうも私には子供をパソコン漬けにする布石を打たれているのではないかと思えてなりません。小学生には読み書きそろばん--というふうに言うと、どうも私の頭の中は古いのでしょうか。
決算特別委員会の席上では、それだけの金額をかけるだけの効果があるのかどうかということを疑問に思いましたので、当局にお尋ねしたところ、手書き学習よりもパソコンを使ったほうが若干学力が上がっているという答弁がありました。
しかし、平成19年度から始めたばかりで、実証研究の途中であり、確実にすべての子供について学力が上がると言い切ってしまうには怖さがあると思います。
パソコンを教えるな、パソコンで教えるなとは言いません。経費削減に相当の努力をされているということも伺いましたし、具体的に数字で出ていますのでその努力は認めますが、やはり1億円を超えるお金をかけるのであれば、人間としてどうあるべきかを教えることも大切ではないかというふうに思います。
パソコンは機械であるがゆえに、自分の気に入らない画面を消したり、ゲームで相手をやっつけることもできます。しかし、そういうことは機械に対しては許されても、人間に対しては許されません。今や学校でしか子供同士が顔を合わせる機会が少なくなっている。また、自己中心主義になると、いじめや他人を傷つけることになるのではないかというふうに危惧をしております。機械が人間の心を奪い、人間社会を支配しつつあると言っても過言ではないと、おとといの代表質問で浦先輩議員がおっしゃっておられましたが、まさにそのとおりだと思います。
学校でパソコンを使えるようになって家庭へ帰って来る。それ以前に、今や一家に1台パソコンがあるというような時代になってきています。学校のパソコンは有害サイトにアクセスしないようブロックがかけられていますが、各家庭では必ずしもブロックが施されているとは限りません。
そうした場合、やはり子ども自身に最低限のよしあしを判断させる情報モラル教育、情報道徳教育と言ってもいいと思いますが、そういう教育が重要なのではないでしょうか。便利にパソコンやネットを利用するに当たり、するべきこと、してはいけないことを教えなければならないと思います。そういう教育を現場でしていただいているのかどうか。また、教員の指導力向上を図るためにどのようなことをしているのか。教員が教えるためのフォローはどのようにされているのか、お答えください。
次に、子育て施策についてです。
御答弁いただいたように、本市でもファミリー・サポート・センター事業は重要だと認識していただいていて、活動件数も増加している。お母さん方の需要は高いということです。
国は、少子化対策を掲げて何とか食いとめようとしているようですが、その一方で、御答弁にもあったように、仕事はあげるけどお金は半分出しなさい--何と勝手なことかというふうに思います。今回のような予算なき市町村への事業移管という名の丸投げは、言うこととやることが矛盾をしていますし、地域主権にはほど遠いというふうに思います。
そして、中央省庁の官僚というのは何と適当なことでしょうか。事務連絡で手紙だけ送り、国会では電話をかけたと答弁をしておきながら、電話はなし、説明会もなし。現場で受ける自治体は物すごく大変です。
この点、経済状況が悪化していることに伴って、共働きの家庭が結果としてふえ、ファミリー・サポート・センター事業の拡充が求められている中で、利用者のいる地域事情を無視した、こういう画一的な再編をどのように思われますか、お答えをいただきたいと思います。
以上で第2問といたします。
《大橋市長 答弁》
地域事情を無視した国によるファミリー・サポート・センター事業の再編についてどう思うかということであります。
国が緊急サポートネットワーク事業を廃止して市町村が実施するファミリー・サポート・センター事業に統合し、さらに、その財源もおよそ2分の1を市町村の負担とする方針を一方的に打ち出したことにつきましては、国が新規事業を立ち上げて、定着した後、国としては事業を廃止して市町村に押しつける、こういうパターンというのはこれまでにも幾つも例がありまして、私としても非常に納得のいかないところでありますが、子育て支援における市民のニーズが多様化していることを考えますと、病気のお子さんや病後のお子さんの預かり及び緊急時の一時預かり等を行う緊急サポートネットワーク事業は、子育て中の市民の方々を支援する上で重要な事業ですので、本市としても引き継がないわけにいかないので、事業を国から引き継いで行う必要があると考えております。
国に対しましては、財源の確保等について機会があるごとに働きかけていきたいと考えております。
以上でございます。
《大江教育長 答弁》
教育施策について、子供たちへの情報モラル教育をしているのかどうか、教員の指導力向上を図るためにどのようなことをしているのか、また、教員が教えるためのフォローはどのようにしているかとの御質問です。
情報モラル教育につきましては、情報社会において的確な判断ができる児童生徒を育成するために、インターネットの正しい活用方法やネット上のいじめなどの危険性について、すべての小中学校において指導しているところです。
教員の指導力向上のために、初任者研修、5年経験者研修でそれぞれ1講座、情報教育担当者研修2講座、選択できる研修を3講座実施しております。
また、カリキュラム、指導実践例、資料などが掲載された冊子を配布するとともに、授業で活用することのできる教材などを提供するなど、フォローしながら指導力向上に努めております。
今後もさらに研修の内容を充実していくよう努めてまいります。
以上でございます。
《再々質問》
それぞれお答えをいただきましたので、第3問に入らせていただきます。
まず教育についてです。
教員に対しては、新任者、そして5年目の教員が全員必ず情報モラル研修を受けると御答弁をいただきました。教員に対してはかなり充実をしていると思います。しかし、子供たちに対しては、道徳の時間のうち年間2こま程度、また、折に触れての教育ということで、これはかなり少ないのではないかというふうに思います。パソコンやネットに触れる割合からすればどう考えても少ないと思います。
さまざまな危険がネット上に存在し、それにかかわる事件も起きていることは既に周知のとおりです。それらから大人が子供を守るということはもとより、子供自身にもみずからを守る能力を持たせなくてはならないと思います。パソコンによる教育を進めること、また、それと同じだけ情報に対する道徳教育を行っていただきたいというふうに思います。
また同時に、家庭でもパソコンに触れる機会が一層ふえてきます。保護者に対しても情報道徳教育、また、普通の道徳教育を受ける機会をつくるべきではないでしょうか。教育は決して学校任せではいけないと思います。これらのことを強くお願いをいたします。
最後に子育てについてですが、一方的な事業の押しつけと経費の約50%負担について、市長から納得いかないと御答弁をいただいたように、私も納得はしていません。
国は、制度を充実させるという口で、金は半分自分で出せと言い、また、地方財政健全化法という網をかけて自治体を追い込んでいく。まさに自己矛盾で、国は一体何がしたいんだ、地方をどうしたいんだと強く感じるわけであります。
病児・病後児保育を行うには普通よりお金がかかります。構造的に赤字になりやすい。それでもやらなくてはならない事業です。また、事業を進めるに当たって、子供の預かり手となるスタッフの専門性の向上やリスク管理を強化することも課題となっています。
保育所との連携も欠いてはいけないことです。ファミリー・サポート・センター事業では、子供を預かってくださる方のサポート、子供に何かあったときのホットラインの設置など、つまりサポーターのサポート体制、これをしっかり組むことも考えなくてはなりません。
事業自体を否定するわけではありませんし、もっと拡充していただきたい。ファミリー・サポート・センター事業は、にわか里親制度と名づけてもいいぐらいで、人間関係が希薄になりつつある社会で、社会が子供を見てくれるいい制度だと思います。ちゃんとせえと国に言うと市長から御答弁をいただきましたので、ちゃんと言っていただけることを心待ちにして、質問を終わらせていただきます。御清聴ありがとうございました。
|
| |
|
今日から一般質問
議会は今日から一般質問に入ります。午前・午後あわせて3人が登壇します。
今日のお昼にはテレビ和歌山で、昨日の代表質問の模様が再放送されていました。各会派の幹事長によるインタビュー、質問者の質問と答弁のダイジェストが放送されていました。
時々議席がアップにされ、私も何回か映っていました。眠たそうな目をしているように見えたかもしれませんが、花粉症で目がかゆく、目薬を点しながら戦っていたのであって、決して眠たいのではありません。
私は明日の3番目に登壇です。今日のお昼に読み原稿を提出しました。それを受けて市当局の勉強会が行われます。
出した原稿があんまり良くなかったので、手直ししていたら20時半になってしまいました。たまにはそんな時もあるんですよ。
|
| |
|
代表質問が行われました。
《告知》
今日行われた和歌山市議会の代表質問の模様がテレビ和歌山で放映されます。明日5日正午から1時間です。ぜひご覧下さい。
今日の議会は各会派の代表者による質問が行われました。この質問は「代表質問」といわれ、いつも私が行っている一般質問とは違います。
どこが違うかと言うと、各会派につき1名しか質問できません。今の市議会には7会派あるのですが、一人会派はできないので、6人が登壇しました。
時間制限があります。時間は会派に所属する議員の数で比例配分します。
1回しか質問できません。当然市当局の答えも1回しかもらえません。
代表質問は、新年度予算が審議される2月議会にしかありません。厳密に言えば、新しい市長が選挙で選ばれたときもありますが、まだそんな場面には遭遇していません。
私が所属する民主クラブは〆木先生が質問に登壇されました。今回の代表質問は教育や子育てを取り上げたものが多かったです。私も一般質問は教育と子育てについてです。
15時半頃に本会議が終わり、質問の最終調整と質問の原稿を書き始めました。なかなか思ったように進みません。
昨日から小沢代表の秘書が東京地検特捜部に逮捕されたニュースが流れています。夕方県連に寄ったら、「記者会見でよく言った!潔い」といった電話が数本入ったそうですが、批判の電話は1本もなかったそうです。国民の皆さんはかなり冷静に見て下さっているようです。
夜にはおどるんやのコーディネーター会議が行われ、参加しました。色々と議論は尽きず、終わったら22時半を回っていました。
ちなみに、私の一般質問は6日(金)13時からです。ぜひ市議会を傍聴なさって下さい。
|
| |
|
本会議、実行委員会
残念ながら、今朝も街頭演説はナシです。申し訳ありません。
朝から市役所にいました。今日は一日中本会議です。午前中は08年度補正予算の審議で、各委員会に割り振られた議案審査の結果について、各委員会から報告がありました。建設企業委員会の報告は私がさせていただきました。
その後、委員長の報告に対して質疑、討論と続きますが、質疑はありませんでした。共産党から一部の議案に対して反対の討論がありました。それから採決となり、賛成多数ないしは賛成全員で全ての議案が可決されました。
お昼休憩を挟んで、午後の本会議は09年度当初予算の提案理由の説明が行われました。それぞれの担当部署別に、何のためにいくら使うのかを説明していきます。事細かに説明するわけではないのですが、それでもかなり時間がかかります。途中休憩しながら16時過ぎまでやりました。
本会議が始まる前や休憩中、本会議が終わった後は市当局と質問の調整です。入れ替わり立ち代り引っ切り無しに担当者がやってきました。
18時過ぎに市役所を出て、一度家に戻ってから、おどるんやのお祭りスタッフ部会に行きました。部会としては久しぶりの集まりです。
今年、私は実行委員会の中でスタッフ担当のコーディネーターという重役をいただきました。衆議院総選挙のある年なので固辞したのですが、杉谷実行委員長のプッシュでさせていただくことになりました。昨年の副実行委員長からバトンタッチして、杉谷実行委員長に今年の祭りの概要をお話していただき、4月5日に行う「おどるんや春祭り」でどんな活動をするのか、話し合いました。
結構、取りまとめ役に慣れているかと思ったのですが、思った以上に自分が慣れていない、忘れてしまっていることが分かり、ちょっと苦労しました。
今日、市行政経営課から「転入・転出臨時サービスコーナーの設置について」と「20年度1課1提案について」の報告が届きましたので、データベースに置いておきます。
|
| |
|
夜まで缶詰
今日は月曜日で、和駅前の街頭演説の日ですが、自転車もトラメガもまだ復活していないので、出来ませんでした。
今日の議会は休会でしたが、一般質問の準備があるので、市役所に入りました。夜まで市役所で缶詰になりました。
夜にはJCの委員会があり、9月に行なう交流事業をどう運営するか、話し合いました。
|
| |
|
つな文
今朝は10時から吉田にある県立体育館で行われた第32回障害児者家族のつながりを広める文化祭にお邪魔しました。昨年から2回目の参加です。ステージ前の椅子に座って、開会セレモニーを拝見しました。
参加される皆さんの中では、この文化祭のことを「つな文」と言っておられるそうです。来年からは私も「つな文」と呼ばせてもらいます。
去年の「つな文」から以降、それぞれの学校で色々な作品を作られ、所狭しと展示されていました。市役所の職員さんがステージでの演奏などをサポートするボランティアをされていたり、本当に手作りの文化祭です。来年もどんな作品が並ぶのか、舞台で楽しませてくれるのか楽しみです。
文化祭の会場を後にして市役所へ。少しだけ質問の資料調べをしました。
その後は和駅から電車で京都へ向かいました。「がんばろう、日本!」国民協議会主催の第16回関西政経セミナーに参加するためです。今回は『低炭素化時代の日本の課題』というテーマで京都大学大学院准教授の諸富徹先生からご講演をいただいた後、数名のパネリストでパネルディスカッションが行われました。
セミナーの後の意見交換会では、挨拶させていただく機会も得ました。ありがとうございました。前回の京都市長選挙に立候補した前市会議員のスタッフをしていた方とお話させていただきました。その候補者さんが書かれた本を私も読んでいて、本の基礎データとなったアンケートを取りにお家を回られたそうです。大変なご苦労があったと思います。
会が終わってそのまま和歌山へとんぼ返りしました。何かと慌しい一日でした。
|
| |