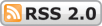|
議会運営委員会
今日は議会運営委員会、略して議運が開かれました。
私は委員ではありませんが、議運で諮られた内容を会派に持ち帰って、全員で協議し、その回答を再び議運へ持っていって協議するなどの手続きがあるので、登庁していました。
会派としての賛否を確認したり、意見書の文案を確認したりしました。
9月も今日で終わり。いよいよ今年も残り3ヶ月になりました。早いものです。
|
| |
|
環境保全対策特別委員会
今日の議会は、環境保全対策特別委員会が開かれました。
市当局からは、昨年度の和歌山市の環境についてまとめた報告書に基づいて委員会で説明を受け、各委員から質疑が行われました。
目標値に達していない環境基準もありますが、計画を立てて、改善していくようです。
|
| |
|
交通政策研究集会
今日は和歌山県交通運輸産業労働組合協議会から民主党県連に講師派遣のご依頼があり、白浜まで行ってきました。
本当はもっと県連の役員や年長で話せる人が行くべきだったのですが、あいにく議会中ということもあり、私しか出られるものがいなくて、一番ショボいのが行かせていただいた次第です。
朝7時半過ぎに県連へ行き、印刷機を回し始めました。前日に追い込まれてレジュメを作り、配布資料をまとめて、ようやく段取りがつきました。なので、朝から印刷です。印刷が終わり、1セットずつホッチキス止めをして、完了したのが9時半でした。
息つく暇もなく自転車で和駅へ。10時5分発のオーシャンアローで白浜へ向かいました。電車の中ではレジュメと資料を見ながら、お話しすることのおさらいをしました。そんなことしてるとあっという間に白浜でした。
駅前から明光バスに乗り、とれとれ市場へ向かいました。おいしい海の幸のお昼を食べたいと思い、行ってきました。
月曜のお昼にも関わらず、団体のお客さんなどたくさんの方がいらしてました。市場内をぐるっと一周して、とれとれ横丁という食事エリアに行きました。色々な種類の海鮮丼があったのですが、私は写真の「堅田(かたた)丼」をいただきました。堅田丼はとろろをかけたご飯にカンパチのづけを乗せた丼です。おいしくいただきました。
それから再びバスで講演の会場へ。雨の予報でしたが、晴れてとても暑かったです。バス停から歩いていくと、私が車で来ると思っていたらしく、役員の方が驚いていました。もともと公共交通好きだというのもあり、やっぱり電車・バスです。
主催者からは「政治情勢について」というテーマをいただいていたので、総選挙以後の政治情勢や、マニフェストの中でも特に交通政策に関わる高速道路の無料化や子ども手当について、お話しました。質疑応答では、もっと突っ込んだ質問や、給食の民間委託についての質問がありました。
つたない話ではありましたが、よく聞いて下さっていました。ありがとうございました。直接本人に率直な感想を言うことはできないと思うので、遠まわしに伺ってみたいと思います。
|
| |
|
命のバトンをつなぐ人が増える
今朝は、消防局で行なわれた普通救命講習に行ってきました。
たいていはこう書くと講習を受けに行ったと思われると思いますが、今回は講師として参加させていただきました。しかし、講師として参加するといっても、私にとってはこれも研修の一環です。
プロフィールにも書いていますが、私は「応急手当普及員」という資格を持っています。この資格は、普通救命講習の講習会を行うことができ、普及員の開講する講習会を受講すると、消防署で受ける講習と同じように、修了証がもらえます。
しかし、実は今回私が講師をしたのには理由があり、応急手当普及員の資格にも更新があります。更新は3年に1回と決まっていて、今年がその年でした。
心肺蘇生法のやり方も変わってきていますし、自分達教える側の技術維持や向上も必要で、それらを学ぶために更新制度があり、今回は実践で学び、向上させることになりました。
全部で30人の受講者がいらっしゃいましたが、そのうちの10人を担当させていただきました。軽く私がデモンストレーションをして、受講生の皆さんに人形を使って練習していただきました。
一巡した後、今度はAEDのデモ機を持ってきて、色々なシチュエーションを想定して、練習していただきました。
私が資格を取得したときは、人工呼吸2回に対して心臓マッサージ15回が1サイクルで、このサイクルを効率良く続けられるよう、傷病者に対する立ち位置などを習いました。
ところが今は、心臓マッサージに重点が置かれ、呼吸よりも血液の循環を止めてはならないというのが救命の理念になっています。
そもそも、私が応急手当普及員の資格を取ったのは、私がお世話になったある方の教えに沿ったからです。見知らぬ誰かのためではなく、自分の大切な人や家族のために、救命の技術を持っていて欲しいと、その方の住む街で普及活動をされています。目標は街の人全員が救命の技術を持っていること。何かあってもお互いに助け合える街を創るのが目標と、私に話してくれました。
私はとても共感を覚え、まずは真似をするところから始めようと、普通救命の講習を受け、上級の講習を受け、普及員の資格を取りました。
理想は和歌山市民全員が、目標は市民の半分が救命の技術を持っていること。目標に近づけるだけの活動を十分に行えていませんが、一人でも増やしていければと思います。
ぜひ、皆さんも普通救命講習を受講して下さい。そして、命のバトンをつなげられる人になって下さい。お願いします。
|
| |
|
いこら会の総会
今日は、郵便局を退職された方が集まる「いこら会」の総会があり、来賓として呼んで下さり、参加しました。
いこら会の皆さんには、私の選挙前からお世話になり、毎年の総会には必ず声を掛けて下さいます。今年の総会には、岸本代議士も参加され、総選挙当選の報告と、ここ数日の国会でのことをお話しされました。
私は、地方議会を主眼において、これからは国会と地方議会の「ねじれ現象」が見られるようになるとお話ししました。今回の総選挙で衆議院では絶対安定多数を確保し、参議院では多数の第一党になっています。これまでの衆参における勢力差のねじれは解消されました。
しかし、国会は選挙が行なわれ勢力が変わっても、地方議会の勢力は変わっていません。例えば、和歌山県議会は定数46名中29名が自民党です。国会で決まった政策に対して、自民党多数の地方議会が抵抗することは、十二分に考えられます。
ただ単に「篭城」するだけなら、政党間の政争に市民を巻き込んでしまい、そのことは市民にメリットがなく、市民目線の政治ではありません。地方議会にも適当な緊張関係がなければならないと思いますし、是々非々での議論が求められるようになると思います。決して、民主党だから白紙委任と言うことではなく、あくまでも和歌山市の状況を中心に議論していこうと考えています、といったようなお話をさせていただきました。
いこら会には、辻田さんという方がいらして、この会の前の会長をされていました。辻田さんは太公望でしょっちゅう釣りに出かけられていたそうです。しかし、昨年の冬、釣りの最中に亡くなられました。大好きな釣りの最中ということで、辻田さんにとっては本望だったのかも知れませんが、そのお顔が見当たらなくて、とても寂しく感じました。
いこら会の総会でご挨拶をさせていただいた後、退席させていただいて、民主党県連の役員会に出席しました。まもなく県内各地で行なわれる首長・議会議員選挙について協議しました。
|
| |
|
委員会審査2日目
今日は委員会審査の2日目です。市長公室および総務局の議案について審査を行いました。
市長公室からは、国の2次補正予算で出る地域活性化・経済危機対策臨時交付金を使った事業で、災害発生時に使用するビニールシートや簡易アルミ寝袋、可動式浄水器などを購入する議案が出されています。
総務局からは、同じく臨時交付金を使って、インフルエンザ対策の使い捨てマスク9万枚を購入する議案が出ています。
明日は討論と採決が行われます。
|
| |
|
取ったら勝ち!
今日はJC青年会議所の鬼ごっこ大会の日でした。インフルエンザが蔓延して、中止せざるを得なくなったらどうしようか、などと思っていましたが、予定通り32チームが集まって、無事開催することができました。
鬼ごっこと言っても、数人の中から鬼を決めて捕まえる、公園で遊んだ鬼ごっこではありません。ゲームは2チーム対抗で行われます。1チーム9人で組織され、お互いに自分達の陣地を与えられます。円の中に置かれた台の上に置いてある宝を取ったら1点。これを何回取るかを競うゲームです。チームワークと作戦力、瞬発力がポイントです。
この鬼ごっこを考案したのが、東京の青山にあるこどもの城で企画研修部長をされている羽崎泰男さんです。NHK教育の番組にもよく出演されていらっしゃって、知る人ぞ知る有名人です。
私はルール説明のときのデモゲームに参加しました。あとは本部で運営と、対戦表の管理を、同じ委員会のメンバーとしました。
羽崎先生がこの鬼ごっこを考案されたのは、クラブ活動などスポーツで技術や練習が必要なくても、気軽に楽しく子どもが身体を動かせるものはないかと考えて、考案されました。
1チーム9人にするために、JCメンバーが数人加わりましたが、見たところ完全に子ども達に翻弄されていました。大人の方が勝てると思いきや、実際はそんなことはありませんでした。
大会が終わった後、JCメンバーが委員会対抗で鬼ごっこをやりました。みんなかなりハッスルしていました。
私は羽崎先生を和駅までお送りする役を仰せつかりました。車中で羽崎先生は、「ここまでできるとは思わなかった。みんな活気のある青年ばかりで、すばらしい」とおっしゃっておられました。また和歌山の環境を気に入って下さって、今度はプライベートで来たいとも言って下さいました。
無事、成功して良かったです。ご参加下さった皆さん、ありがとうございました。JCメンバーの皆さん、お疲れ様でした。
|
| |
|
明日は鬼ごっこ
今日の夕方、JC青年会議所のメンバーがビッグホエールに集まって、明日行なう和歌山鬼ごっこ大会の準備をしました。
ラインテープを引いてコートを作るのですが、ゆがんだり、だぶついたりして、これがなかなか難しいんです。
後は明日に備えるばかりです。
|
| |
|
突然の訪問
先日亡くなった元岩國事務所の事務所長のお宅へ伺いました。手を合わさせてもらおうと思ったのですが、ちょうど故郷へお骨を持っていくところで、機会を得ることができませんでした。残念でなりません。
午後からは、同じく元岩國事務所の幹事長のお宅へ伺いました。事前に電話を差し上げたのですがつながらず、結果として突然の訪問になってしまったのですが、温かく迎え入れて下さいました。
最近のお話を色々と伺うことができました。また超がつくほどのベテランから見た総選挙をどう分析するかも聞かせていただきました。
それにしても、関わりのあった方が亡くなるというのは、本当に寂しいことです。
|
| |
|
ぶっ通しの議論
昨日の夜の最終フライトで東京へ来て、今日は朝10時から「がんばろう、日本!」国民協議会の勉強会に出席しました。
主なテーマは衆議院総選挙後、民主党中心の政権になって、地方議会はどうあるべきかを中心にたくさんの方がお話されました。
私も発言の機会を与えられて、和歌山での選挙の経過と結果、そして自分なりに、これからの新政権下で地方議員としてどう動こうと思っているかをお話しました。中身は9月16日の「明日はどっちだ!?」で書いたとおりです。
お昼休憩を20分ばかし取っただけで、後はぶっ通しでした。議論を始めれば、案外時間が経つのは早いものです。
|
| |
|
今日から委員会審査
昨日の本会議で、市当局から提出された議案が、それぞれの委員会へと分野別に担当分けされました。これを「委員会付託」と言います。和歌山市議会では4つの委員会に分けて議案を審査しています。
総務委員会では、市に関わる全ての歳入と、財政局や総務局、市長公室などの歳出が審査対象です。今回は麻生内閣が行った2次補正予算による歳入と歳出が上程されています。
副委員長は運営に徹して、余り質問しないと言う暗黙の了解になっているのですが、どうしても聞いておきたい事があり、財政局の審査の際に質問しました。
今回の歳入には、春に行われる予定だった大阪・神戸へ行く小学校の校外学習が、インフルエンザ蔓延のために中止となり、そのキャンセル料約176万円が計上されています。
「地域活性化・経済危機対策臨時交付金」としてそのお金が交付されているのですが、(そもそもキャンセル料が「地域活性化・経済危機対策」なのかが分からないですが…)これから修学旅行の時期とインフルエンザの第2波が重なって、当然キャンセルの発生も予測されるのですが、そういう緊急の事態に対応できるように、予算の確保をお願いしました。当局からも何とか努力する旨の答弁をいただきました。
春はたまたまですが2次補正の予算があったからキャンセル料が保護者負担にならず、秋の修学旅行は保護者負担になると言うのは整合性に欠けます。また修学旅行の方が日数も長く、キャンセル料も高額になります。なんとかしたいと思います。
委員会は連休明け、再開です。
|
| |
|
一般質問の最終日
今日の議会は、一般質問の最終日でした。今日も先輩議員3人が登壇しました。
夜にはJC青年会議所の臨時委員会が行われました。23日に鬼ごっこ大会を行うのですが、その最終の詰めです。
今朝、岩國事務所時代の後輩秘書から連絡がありました。私も現役時代、ずっとお世話になった事務所の事務所長が亡くなられたそうです。
前回、議員会館でお会いしたとき、げっそりされていて、病気だということまではお伺いしていたのですが、それ以上は詳しく聞きませんでした。
代議士が世田谷で出られたときから尽力されていらっしゃいました。心から敬意とご冥福をお祈りします。
|
| |
|
分厚い書類
昨日、一般質問を終えました。傍聴者もいませんでしたが、マスコミの方もいませんでした。和歌山地裁で裁判員裁判をやっていたので、そちらの取材に行ってしまわれたのでしょう。でも、変わらずちゃんと質問させていただきました。
今日も引き続き、一般質問が行われました。鳩山総理の誕生、そして組閣の日とあって、気もそぞろでした。午前中に3人目の1問目の質問と答弁まで終わりました。13時から再開して、13時45分には今日の本会議が終わりました。
14時から民主党の友誼団体の総会が行われ、出席しました。私はその団体の会計監査を仰せつかっていて、監査報告をさせていただきました。
総会が15時ちょっと前に終わって、慌てて県連へ行き、テレビをつけましたが、鳩山さんが選ばれた瞬間には間に合いませんでした。残念。
役所に戻ると分厚い封筒が届いていました。中身は平成20年度の決算報告書です。公営企業の報告書と一緒に並べて定規で厚さを測ってみました。ほぼ6センチありました。余りの分厚さに、思わず写真を撮りました。またこの報告書を、眼を皿のようにして見なくてはなりません。
その後、一度家に戻ってから、友誼団体の懇親会へ参加しました。
|
| |
|
09年9月議会の一般質問全文
今日の質問の議事録を記します。なお、これは原稿ベースで、速報版です。実際の議事録は若干異なることをお含み置きください。正規は後に発行される議事録に拠ります。
《質問》
民主クラブの山本忠相です。今回は本市における身体障害者の雇用について、及び公営住宅について質問をさせていただきます。
まず、本市における身体障害者の雇用についてです。
医療や介護技術の飛躍的な向上によって、障害を持たれた方でも、社会進出が可能となり、社会の一員として活き活きと活躍される方も多くなってきました。
このような状況を鑑み、厚生労働省でも障害者の社会進出を妨げてはならない、より一層推し進めるべきとの考えで、「障害者の雇用の促進等に関する法律」を改正してきました。
この「障害者の雇用の促進等に関する法律」は昭和35年に成立したものですが、それから幾度となく改正され、直近では今年の7月15日に改正されています。
この法律には、障害者に職業を紹介すること、就業や生活支援を行うこと、身体障害者および知的障害者の雇用義務などが定められています。
その中に、民間企業や特殊法人、国や地方公共団体に対して、一定数以上の障害者の雇用が具体的な数字で定められています。これを法定雇用率といいますが、常用労働者数56人以上規模の民間企業では1.8%。常用労働者数48人以上規模の特殊法人では2.1%。職員数48人以上の国や地方公共団体に対しは2.1%。うち、職員数50人以上の都道府県等の教育委員会は2.0%という法定雇用率が設定されています。
今年の4月に施行された法改正の背景には、2つの要因があります。
まず一つ目は、障害者の勤労意欲の高まりです。厚労省の調査では、障害者の求職件数は1998年に7万8千件だったものが、2007年には10万7千件と37%余り増加しました。また実際に就職した件数は98年で2万6千件だったものが、07年には4万6千件と約77%増加しました。
一方で課題もあります。大企業では障害者雇用が増加している反面、地域の身近な雇用の場である中小企業での雇用が低下してきているのです。100人から299人の従業員を抱える企業の実雇用率が一番低いのです。
2つ目は、短時間労働への対応です。障害をお持ちの方は体調に左右されたり、また診療やリハビリのために通院することもあり、フルタイムの勤務よりパートのような短時間勤務を好む傾向が一部にあります。しかし、これまでの法律では短時間労働に対応できていなかったため、雇用主は週30時間勤務の常用雇用を基本とし、現状で短時間労働者を受け入れる利点に乏しかったのが現状です。
これら2つの要因を踏まえて、来年7月1日から、中小企業における障害者雇用の促進と、短時間労働に対応した雇用率の見直しなどが追加されることになりました。
これら法律と環境の整備が整えられつつある中で、本市においては、この法律に対しどのように対応してきたのでしょうか。また、本市における障害者雇用の現状はどうなっていますか。正規職員、非常勤職員も含めてお答え下さい。
次に、公営住宅についてです。
先ごろ、公営住宅が注目される出来事がありました。リーマン・ショックから波及した経済不況によって会社から解雇され、会社の寮を放り出された派遣労働者の受け皿となったのが公営住宅でありました。
しかし、これより前に公営住宅の課題・問題点で注目され始めていました。それが「住民の少子高齢化」と「建物の老朽化」です。
高度経済成長期前後に建設された団地が老朽化し、スラム化しつつあるという問題が表面化し始めました。有名なところでは、大阪の千里ニュータウンで、1962年11月に街開きを行って以降、順調に人口を伸ばしてきました。しかし1980年代を境に、人口は減少傾向にあるものの、世帯数は増加の傾向をたどりました。これは1世帯当たりの構成人数が減っていることを表しています。
ニュータウン完成時までに入居した家族の多くが、30~40歳代の世帯主を中心とする家族で、その子ども達が現在は成長して独立し、ニュータウンの外に住むようになったため、入居者の高齢化が進みました。
また若い夫婦が居住しても子どもが少なかったり、いなかったりするために少子化が進みつつあります。
和歌山市に眼を向けてみます。本市においても、市内にある団地の多くが老朽化し、耐用年数を大幅に過ぎた建物が多数存在しています。
当局からいただいた資料を少し分析してみました。すると、和歌山市の公営住宅の中で今年耐用年限を過ぎたものが29団地1043戸。うち10年以上過ぎてしまっているものが800戸余りありました。資料を元に自分で調べたので、間違っていたら指摘してください。
団地に住む人についても、先程お話した千里ニュータウンと傾向は同じです。団地の完成時に入居した30~40歳代の世帯主が、そのまま高齢化してしまっています。また公営住宅は収入の制限があり、比較的高額の年金を受け取れる方は、団地から出て行ってしまいました。
このように高齢者や低所得者だけが団地に取り残されて、以前のような「まち」や「むら」といったコミュニティを維持できない状態になっていると考えます。
そこで、このような現状を当局はどのように認識していますか。
以上をお伺いして、第1問といたします。
《笠野総務局長 答弁》
障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく障害者の法定雇用率は、官公庁が2.1%、教育委員会が2.0%、水道局が2.1%で、それぞれが事業所として位置づけられています。
本市では、障害者の雇用の促進を図るため、平成17年度から身体障害者を対象とした特別枠の採用試験を実施し、毎年1名ずつの身体障害者を採用し、また、平成19年度からは知的障害者を対象とした特別枠の非常勤職員採用試験を実施し、毎年1名ずつの知的障害者を採用しているところです。
また、非常勤職員及び賃金支弁職員につきましては、法定雇用率には算入できませんが、本人の申し出等により把握している限りで6名の障害者を雇用しています。さらに、採用された職員の能力が十分発揮できるよう、職場の環境づくりを行い、雇用の安定を図るよう努めているところです。
このことにより、本市の平成21年6月1日現在における雇用率は、市長部局では2.51%、教育委員会では2.47%、水道局では2.43%であり、いずれも法定雇用率を上回っています。
《千賀建設局長 答弁》
現在、住宅部において管理している市営住宅の中には、建築後かなりの年数が経過している団地も多くあります。また、団地の居住者も少子化が進み、高齢者世帯等がふえているという現状につきましては、今、例示されました事例と同様でありまして、その点につきましては十分認識してございます。
つきましては、今後、老朽化が著しい団地の建てかえの際には、世代間の交流を図り、バランスのとれたコミュニティーを再生、維持することができるよう努めてまいります。
《再質問》
まず、本市における身体障害者の雇用についてです。
ご答弁にありましたが、本市の雇用率は6月1日現在、市長部局2.51%、教育委員会で2.47%、水道局2.43%で、いずれも法定雇用率2.1%を超えているとのことです。
法定雇用率を超えてはいますが、決して褒められる数字ではないと思います。
さて、ここで民間企業での事例をご紹介します。
2007年11月東京都武蔵野市にある横河電機㈱へ視察に伺いました。横河電機では横河ファウンドリー㈱という特例子会社を設立し、そこに21名の知的障害者の方がお勤めになっています。彼らは横河電機や関連会社から発注される名刺やスタンプの製造、ファイルのリサイクル、社内で発生した古紙やゴミの回収、請求書や資料の封詰め、廃機器の解体分別などを請け負っています。
横河電機本社のロビーで待っていると、実際に働いている知的障害の方が迎えに来て下さり、職場まで案内して下さいました。職場では業務を担当している人が、それぞれに自分のしている仕事を説明して下さいました。後に人事担当(横河電機では「人財部」と言います)の方から聞いた話ですが、見学者に対する説明は会社からこう言いなさいと決めているのではなく、各人がそれぞれに自分で考え、説明しているとのことでした。また、例えば、スタンプを作る人の場合、小さいスペースに漢字がたくさん並ぶと、字がつぶれて見えにくいので、書体を漢字だけ教科書体に変えるなど、それぞれに工夫をする余地が与えられていました。
ただ単にマニュアル通りこなすだけの仕事ではなく、それぞれに工夫し考える余地を与えることで、あくまでも自立の一助になるように、との配慮がなされていました。また、一つの業務に偏ることがないよう、複数の業務ができるように訓練されているそうです。これは、別の社会に出たとき、一つのことしかできないよりもいくつかのことができるほうが、道が広がるという配慮からです。
本市では採用した障害者を組織の中に取り入れて、障害者が市役所に合わせるというやり方になっています。しかし、横河電機ではその逆で、障害者が活躍できる職場を会社が作る、つまり会社が障害者に合わせているのです。
横河電機の事例を参考に、名刺やスタンプの製造、ファイルのリサイクル、庁内で発生した古紙やゴミの回収、請求書や資料の封詰め、廃機器の解体分別などを専門に行なうチームを作ったりして、対応できないでしょうか。
次に、公営住宅についてです。
先のご答弁の中で、高齢世帯等が増えている現状を十分認識しているとお答えをいただきました。問題は認識したその次です。次の一手をどう打つのか。バランスの取れたコミュニティを再生・維持することができるよう努められるともお答えいただきました。
では、具体的にコミュニティを再生・維持する策はあるのかどうかをお答え下さい。
コミュニティーバランスが取りにくい、口で言うほど簡単に維持していけないという現状は理解しております。例えば、現住者が様々な理由で部屋を移動してくれず、居住者の集約が進まない。財政の課題もあり、なかなか建て替えに着手できない現状も良く分かります。
しかし、それは団地という一つの街に対する当局の先行き・構想・次のプランが示せておらず、漠然と住居の移動をお願いしているからではないでしょうか。
具体的でなくとも、夢物語でもいいと思うんです。団地を中心とした「まち」や「むら」づくりのプラン・ビジョンを示してくことが、住民の理解と協力につながっていくのではないかと思います。
一人のエゴのために、他の多くの方が享受できるであろう快適な住環境を得ることができない。これは公共の福祉を優先するという考え方に反しているのではないかとも思います。
このように、まちづくりのビジョンを示していくことについて、当局の見解をお示し下さい。
《大橋市長 答弁》
先ほど総務局長が御答弁いたしましたとおり、本市は法定雇用率を達成はしていますが、地方公共団体は障害者の雇用等に関する法律に基づいて、民間に率先垂範して法定雇用率を達成、維持することが求められています。障害者の方を採用するときには、特定の障害部位を限定するのではなく、採用された方の障害に応じた職務設計をすることが適切だと言われておりますので、採用された障害を持つ職員が十分取り組める職務を提供するとともに、今後も身体障害者を対象とした特別枠の職員採用試験を継続し、雇用を図ってまいります。
一方、議員御提案の事業所が障害者に合わせた職場づくりを行い、障害者の雇用を促進していくことも重要なことであります。本市におきましても、知的障害者を対象とした非常勤職員の採用試験のときにはその方法を導入しておりますが、今後、一人でも多くの障害者の方が活躍できるよう、職域の拡大を検討してまいります。
《千賀建設局長 答弁》
バランスのとれたコミュニティーの再生、維持を図る主な施策といたしましては、子育て世帯の優先入居や子育て支援施設等の立地誘導による若年世帯の入居促進、みなし特定公共賃貸住宅の活用による中堅所得者層の入居の促進などの方策があります。また、建てかえを契機とした多様な住宅を供給することにより、高齢者世帯や若年者世帯の世代間交流ができると考えます。
今後の住宅政策を進める上で、こうしたコミュニティーは大変重要なことであると考えていますので、団地を中心として地域が生き生きとした町になるよう機能していくためにも、まちづくりのプラン、ビジョンが欠かせないものと思いますので、住民の御理解と御協力をいただきながら取り組んでまいります。
《再々質問》
まず、本市における身体障害者の雇用についてです。
市長から前向きなご答弁をいただきました。これまでのベクトルとは逆のやり方を検討していただけるとのことで、障害者の方々にとってはうれしく、勇気の出るお話だと思います。
障害者に合わせた職場作りという点では、社内ベンチャーならぬ庁内ベンチャーを立ち上げて、役所で発生する仕事を庁内ベンチャーで請けるというやり方も考えられるのではないでしょうか。テクニカルな部分については畠山副市長や山口財政局長が、情報の窓口を東京にお持ちなんじゃないかと思います。
そして、横河電機の担当者もおっしゃっておられましたが、何より大事なのは障害者の能力や特徴と仕事のマッチングです。これが合えば、障害者も活き活きとやりがいを持って仕事に励み、生活できる。役所も仕事がはかどります。合わなければ、両者にとって不幸な結果しか生み出しません。
市役所からの視点か、働く者からの視点か、目線の合わせ方で対応が大きく異なると思います。ぜひ眼に見える形で実現していただけるよう求めます。
最後は、公営住宅についてです。
色々な手法をお答えいただきました。次は市内の団地において、具体的に落としこんでいくことが必要になろうかと思います。何をどのように、と詰めていきたいのですが、第3問ですので、また次回に譲りたいと思います。また、まちづくりに欠かせないと認識していただいたプラン・ビジョンを示していただきたいと思います。
住宅の問題は単に社会基盤としての住宅問題だけでなく、福祉の問題、最低限度の生活を安定して営む人権の問題でもあります。今後も進捗状況を確認し、引き続きこの場で取り上げていきたいと思います。
以上で私の一般質問を終わります。
|
| |
|
今日から一般質問
今日から一般質問が始まりました。全4日間です。私は明日の一番目に登板します。今日も3人の議員が一般質問に登壇しました。
昨日というか、今日の夜中3時までかかって質問の原稿を書き上げて、今朝市当局に渡しました。もう一回推敲します。
|
| |
|
久しぶりの稲刈り
今日は食とみどり・水を守る和歌山労農市民会議主催の稲刈りに参加しました。大人と子ども合わせて20人ほどで稲刈りをしました。
6月に田植えをして、3ヶ月ほどで稲穂がたわわに実っていました。改めて植物の力、自然のすごさを感じました。
参加者の皆さんと一緒に鎌で稲を刈り取りました。稲刈りなんて、小学校での体験学習以来じゃないかと思います。久しくやってなかったです。刈り取った稲は、田んぼを貸してくれた地主の農家さんが脱穀してくれるそうです。その後、アフリカのマリ共和国へ支援米として送られます。
マリ共和国の皆さん、おいしい日本のお米をいっぱい食べて下さいね!
|
| |
|
常任幹事会、政治スクール
10時から民主党県連の常任幹事会が行われました。総選挙後初めての開催ということで、テレビ局のカメラや新聞記者が取材に来ていました。岸本代議士が遅れて到着し、お礼の言葉を述べられました。
14時半からは第2期政治スクールの第4回講義を行いました。今回のテーマは「地方議会はどのように動いているか」です。
きっと分かっているであろうとは思いましたが、国会と地方議会のシステム的な違いなどをお話して、続いて瀧洋一橋本市議会議員が6月議会で行った一般質問のビデオを見ました。
和歌山市議会と橋本市議議会では一般質問のやり方が違います。和歌山市では3回までしか質問はできませんが、時間制限はありません。そして事前に議員と市当局が質問内容に関して、十分な摺り合わせを行います。このやり方のウィークポイントは、議論の過程が不透明なこと。市民に見えないところで議論されてしまいますが、こちらが求める結論には導きやすいです。
一方、橋本市議会は、質問しその答弁を受けた後は一問一答になります。ただし、60分以内という時間制限があります。一問一答ですので、議論の過程が市民の目にもはっきりと分かる一方、必ずしもこちらが欲しい結論に辿り着けず、詰め切れないこともあります。
全部の市町村議会が同じやり方ではなく、それぞれに違いがあるということを知ってもらいました。その後は受講生から質問を受け、それに答えていくと言うやり方をしました。
受講生だけでなく、一般の皆さんにも議会がどういう風に動いているのか、知ってもらいたいとも思いました。
|
| |
|
間に合わない!
14時から議会で、総務委員会正副委員長の勉強会が入っていました。
そこで、羽田を11時半に出て、関空に12時45分に着き、13時発のリムジンバスに乗って13時40分ごろ和駅に到着、そして市役所へ。という日程を頭の中で描いていました。
しかし、羽田を飛び立ったのが20分遅れ。機内アナウンスでは12時50分に到着と言っていたのに、13時に到着。リムジンバスに乗れず、電車でも間に合わない。結局、勉強会の開始を土壇場で30分遅らせてもらうことになりました。ご迷惑かけて本当に申し訳ありません。
あれぐらいの遅れなら取り戻せそうな気がするのですが、ダメなのでしょうか。それともわざと取り戻さないのか。
14時半ちょっと前から、総務委員会に付託される予定の議案について、当局から説明を受けました。
その後は一般質問のすり合わせを行いました。当局からの答弁は全て揃いました。私の原稿は月曜日の朝にお渡しするとお約束しました。当局としては今日欲しいらしかったのですが、無理をお願いしました。この土日のうちにしっかり取り組みます。
|
| |
|
9月議会が開会
今日から9月定例市議会が開会しました。
今議会には市当局から、国の第2次補正予算で市に入る補助金などが計上された補正予算案が出されました。今日はその中身の説明が行なわれました。
14日から一般質問が始まり、私は15日の10時から質問に立ちます。
本会議が終った後は、質問のすり合わせをしました。まだ当局との調整が全部終っていません。その上、私も原稿を書けていない状態です。今回はかなりやりにくく、しんどいです。
この後、和駅からリムジンバスに乗り、関空を経由して東京へ。霞ヶ関で行なわれたスウェーデンの介護制度について学ぶ勉強会に参加しました。
この勉強会は、講義が千葉県松戸市、山梨県市川三郷町、熊本県荒尾市とテレビ電話システムでつなげて質疑応答できるほか、インターネット回線で北海道と三重県にネット配信されています。こんな勉強会は初めてでした。
スウェーデンで行なわれている介護の現状から学ぼうという勉強会で、全部で4回行なわれるうちの、今日は2回目です。1回目は日程が合わず参加できませんでした。
今回は在宅介護や施設での介護の違い、最新の介護現場がどんな風になっているかを教えていただきました。
言うまでもなく、日本の介護とは全く異なります。日本では施設に入れたがることが多いですが、スウェーデンでは自宅か限りなく自宅と同じ環境で介護を受けることが普通です。介護のスタッフは仕事によって細分化されていて、何人ものスタッフが短時間で一人の要介護者に関わります。日本のように一人が一人にべったりという感じではないのです。
とても効率的に合理化されています。しかし、そんな中にも手厚さが感じられます。この差は一体何なんだろうと思いました。
来月もまた講義があります。次回は財源を中心にお話して下さるそうです。
写真は会場となったビルの前の広場です。しばらく来ない間にとてもきれいに整備されていました。なんだか東京の風景だなぁって思いました。
|
| |
|
3新議員との意見交換会
今日は先日の総選挙で選ばれた、新しい和歌山県選出の衆議院議員3人との意見交換会がありました。選挙が終わって3人揃って顔を合わせるのも初めてになります。
それぞれの新議員から選挙のお礼と、これからの抱負を語っていただきました。
その後、引き続いて県の施策や財政の状況についてお話したいと、仁坂県知事から申し出があり、3議員と県知事との懇談会が行われました。
私は冒頭の写真を撮っただけで、同席はしませんでした。知事からは50分ほど説明があり、質疑応答も含めて、1時間40分行われたそうです。
後から懇談会の内容を伺いましたが、説明の範囲が広すぎて、何にポイントをおいて説明したかったのかが、分からなかったそうです。
懇談会が終わってから行われた、3議員の記者会見には途中から入りました。
これからが色々な意味で「動く時」になりそうです。
|
| |
|
難しい問題
今回の一般質問では、2つのことを質問します。昨日の夜は、そのうちのひとつについて関係するお話を聞かせていただきました。
2時間ほどで家へ帰ってきて、それからパソコンに向かったり、本を読んだり。あっという間に夜中の4時でした。
朝は、もう一つの方の質問について、関係する事柄に詳しい方に午前中いっぱいお話を伺いました。なかなかいくつかの問題が重なり、一筋縄では解決しにくい問題です。
|
| |
|
反応アリ
昨日まで2回、私が出演した「FMワカヤマ(バナナFM)」の番組が放送されました。聞いて下さった方からの反応がいくつかあり、本当にうれしいです。ありがとうございました。
一般質問の通告をしましたが、質問がなかなかまとまりません。今回は日程の関係もあるのですが、どうもやりにくいです。
これから、一般質問に関係する情報をお持ちの方とお会いしてきます。
|
| |
|
梅田でミーティング、再生の町
【緊急告知】
和歌山のコミュニティFM「FMワカヤマ(バナナFM)」の『和歌山市議会通信』に出演しました。再放送は明日6日(日)21時からです。FMラジオのチャンネルを「87.7」にあわせて、ぜひお聞き下さい!
今日は久々に大阪へ行ってきました。日本禁煙学会の方と、市議会の禁煙について情報交換するためです。
9時半のサザンに乗って難波で乗り換え、地下鉄で梅田へ向かいました。
JR大阪駅の駅ビルにある大丸梅田店の14階で学会の理事さんとお会いしました。大丸は完全分煙された喫煙室以外は禁煙になっています。普通の人にとっては、とても快適な空間です。
昼食を取りながら、1時間半色々なお話をさせていただきました。
来たときとは逆の順路で和歌山へ戻りました。それから周平事務所へ。選挙の後始末のお手伝いをしました。
今、NHKの土曜ドラマで『再生の町-ふるさとが破綻するとき 私たちは何を守るのか…?-』というドラマが放送されています。全5話で今日2話の放送でした。
先週の放送では、主人公が務めていたデパートが買収されたのを機に、故郷の大阪へ帰ってきて、市役所に再就職した。しかしその矢先、市が財政破綻し、主人公は財政再建プロジェクトチームの一員に加えられ葛藤するという話でした。
和歌山市もほんの少し前まで、破綻の懸念がありました。都市計画税をはじめ、様々な分野で市民の皆さんの負担を増やした結果、今はかなり改善しましたが、決してずっと破綻しない、安全である保障も未来予想もありません。他人事ではないと思いながら、ドラマを見ています。
国営放送ですから、民放が切り込みにくいテーマでもやれるのかなと思います。以前、同じ土曜ドラマのシリーズで監査法人のドラマをご紹介しました。日本の今の姿を見せてくれていると思います。ぜひ皆さんもご覧になって下さい。そして、ご自身の町のこととして考えていただく契機になればと思います。
|
| |
|
今日を短くまとめて
【緊急告知】
和歌山のコミュニティFM「FMワカヤマ(バナナFM)」の『和歌山市議会通信』に出演しました。再放送は6日(日)21時からです。FMラジオのチャンネルを「87.7」にあわせて、ぜひお聞き下さい!
今朝はまず民主党県連に行って、来週の土曜日に行う政治スクールの準備をしました。
11時から県連の三役会議に出席。総選挙後のこれからの動きや日程を確認しました。
市役所へ戻って、市当局にお願いしていたことなどの進捗状況を伺いしました。
その後は、夕方まで民主党県連にいました。ホームグラウンドになりつつあります。
|
| |
|
元気をくれた人
【緊急告知】
和歌山のコミュニティFM「FMワカヤマ(バナナFM)」の『和歌山市議会通信』に出演しました。再放送は6日(日)21時からです。FMラジオのチャンネルを「87.7」にあわせて、ぜひお聞き下さい!
朝から県連や市役所をウロウロしていました。
12時からはクラブ総会が開かれました。いよいよ実質的に9月議会の開会です。質問の詰めもしていかなくてはなりません。
夕方は雑賀崎へ支援者を訪ねました。
19時からはビッグ愛で行われた「和歌山の外食産業を盛り上げる会」3周年記念の例会に参加しました。今回はお好み焼きでおなじみの千房株式会社代表取締役 中井政嗣さんが『お好み焼き日本一の感動経営-情熱と感動が生んだ年商55億円-』 をテーマにお話して下さいました。
子どもの頃に丁稚奉公に出た5年間のこと、お好み焼き千房を立ち上げた時のこと、会社が傾いたときのこと、ちょっと道を逸れた子どもを会社に引き込むのはなぜか、など2時間きっちりお話して下さいました。
自分とちょっと重なる部分があり、同じ考えをされる方がいらしたのだと思いました。そして、お話を伺って、とても元気になりました。ハキハキとした声、たくさんの拍手が元気をくれたのだと思います。次は私が誰かに元気を伝播させる番です。
今日、中井社長さんにお会いできて本当に良かったです。ぜひもう一度お話しを伺いたいと思いました。
|
| |
|
選挙会に出席
【緊急告知】
和歌山のコミュニティFM「FMワカヤマ(バナナFM)」の『和歌山市議会通信』に出演しました。再放送は6日(日)21時からです。FMラジオのチャンネルを「87.7」にあわせて、ぜひお聞き下さい!
10時から県庁で選挙会があり、出席しました。
選挙会とは、選挙の結果を確認し、選挙管理委員会として結果を確定するために行われるものです。私は民主党の代表として選挙立会人に届出し、各小選挙区の選挙会に出ました。同時に比例代表の選挙会と最高裁判所裁判官国民審査審査会も行われました。小選挙区と比例代表の選挙立会人は兼任できないとのことで、小選挙区の選挙会のみ出席です。
1区の岸本周平さん、2区の阪口直人さんの当選が公示され、当選証書が手渡されました。3区の玉置公良さんにも当選証書が手渡されるところを見たかったのですが、残念です。
午後からは、久しぶりにべったり市役所にいました。そろそろ質問の準備もしなければなりません。
夜は、JC青年会議所の委員会が開かれ、出席しました。しばらくアクティブな委員会だったので、久しぶりに椅子と机を使っての委員会でした。23日に行う「鬼ごっこ和歌山大会」の役割分担などを決めました。
今日のラジオを聞いて下さった方はいらっしゃるでしょうか?ぜひご感想などお寄せ下さい。
|
| |
|
FMワカヤマに出演します!
【緊急告知】
明日9月1日16時から、和歌山のコミュニティFM「FMワカヤマ(バナナFM)」の『和歌山市議会通信』に出演します。再放送は6日(日)21時からです。FMラジオのチャンネルを「87.7」にあわせて、ぜひお聞き下さい!
今朝は周平さんと一緒に和駅の中央口に立ちました。昨日と同じように、たくさんの方々が祝福や激励の声を掛けてくれていました。
朝立ちの後は県連へ入りました。私がお世話になっている団体の総会が近々あり、会計監査を仰せつかっているので、帳簿類の点検と監査報告書の作成を行いました。
お昼ご飯を食べた後、13時ちょっと前に、塩屋にあるFMワカヤマのスタジオへ入りました。かけたい曲の確認と、どんなことを話すかの打ち合わせを行って、本番です。
ラジオのスタジオは本当に久しぶりです。前にも書いたと思いますが、高校2年から3年にかけて、WBS和歌山放送ラジオの「ラジ坊」という番組に1年間、パーソナリティーとして出させていただきました。
録音テープが家のどこかにあると思いますが、今では聞くに堪えないウダウダのしゃべりだったのではないかと思うと、公共の電波に流れていたことが正直怖いです。
番組の中では、先日亡くなった父のことや仕事のこと、趣味のことなど、お話させていただきました。本当にとても楽しかったです。
ぜひお聞きになって、ご感想などをお寄せ下さいね。
|
| |