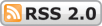|
内航航路の存続、議会改革
今日の午前中は県連やしまくみ事務所へ行ったりしていました。
13時からは南海フェリーの兜社長さんや県の交通政策担当者が、内航航路の存続について陳情するために県連へいらっしゃいました。
3月末まで社会実験として、和歌山・徳島両県の車は1000円というキャンペーンをしていましたが、それも期限が過ぎて終わりました。
一企業体を存続させるためというのではなく、公共交通である内航航路を維持するという観点から、高速道路の均一料金制度などを見直して欲しいとの要望でした。
すでに和歌山と徳島、南海フェリーだけの話ではなく、日本の交通体系で、鉄道やバス、航路をどのように位置づけ、高速道路との関係をどうするかという点まで考えなければなりません。
これまでも要望を受けて考えてきましたが、制度が土日祝1000円から終日2000円均一に変わろうとする今、一層党県連の中で検討しなければならない課題だと思っています。
お話を伺った後、関空を経由して東京へ。虎ノ門にある東京財団で勉強会があり、参加しました。
今回は「地方議会改革は誰のためか~地方議会議員の活動」というテーマです。財団の上席研究員である木下敏之先生が、現役の地方議員にどのような時間の使い方をしているか、30人弱を4ヶ月間追いかけて、それを基に地方議員の活動の「見える化」についてお話して下さいました。
あさっての28日、和歌山市議会では2回目の議員定数問題特別委員会が開かれます。それに先んじて、議員定数や議員報酬について論じるためのヒントを得られればと思い参加しました。
ものすごく簡単に言うと、まずは議会や議員が何をやっているのかをオープンにして、「私の仕事は報酬に見合っていますか?」と市民に判断を求めること、同時に議会自体がもっと市民へ近づいていくことが必要、というのが結論です。
今日のお話を持って帰って、会派で話して、活かしてもらえたらと思っています。
|