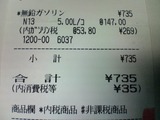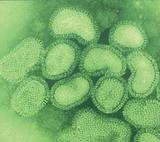国民一人ひとりのため、私は逃げずに立ち向かう
衆議院議員 馬淵澄夫
3・11で日本は決定的に変容してしまいました。津波ですべてを洗い流された東北の農山漁村の光景、原子力災害で不幸にして行き場を失わざるを得なかった福島の住民の皆さんの姿をみて、明治維新以来幾多の困難を乗り越えて積み重ねてきたわが国近現代の歩みを見つめ直さなければならない、と感じた方も多いのではないでしょうか。あの大震災のとき、どんなに生活が豊かで便利になっても、私たちは人と人とのつながりのなかでしか生きられないのだ、という当たり前のことを私はしみじみと感じました。6人の子どもを持つ親として、両親と妻の母親と暮らす大家族の一員として、人と人とのつながりこそ、これからの日本の復興・発展のための基礎となる不変の価値観、拠り所なのだということを再認識致しました。
今、国民一人ひとりが家族のようにお互いに身を寄せ合って、地域のみんなで協力しながら、逞しく、そして凛として復興に立ち上がろうとしているときに、わが国の政治の有様はどうでしょうか。こういうときこそ、前例や既成概念を超えて、思い切った対応を、スピード感を持って実行することが必要です。政治家は、逃げたり、あるいは行政のせいにするのではなく、全責任を背負う覚悟で仕事をすることが必要なのです。それが、私たちがあの2年前の暑い夏、全国で国民に訴えてきた「政治主導」の政権運営であり、「国民の生活が第一」ということであったのではないでしょうか。残念ながら今の私たちの政権運営は、政権交代の原点からかけ離れており、胸を張って国民に報告できるものではありません。
政権交代前の私たちがなぜ国民から期待されたのでしょうか。私たちは結党以来、常に、天下り、税金の無駄遣い、耐震偽装や道路整備の問題に見られる際限なき裁量行政、あるいは不作為の連鎖による無責任体制を地道に調査し、国会で質し、長きにわたる政権支配で腐敗しきってしまったこの国の権力構造を変えることを訴え、国民の皆さんから支持されてきました。そして、国民の皆さんにマニフェストを提示し、実現を約束して参りました。これまでマニフェストが実現できなかったのは、マニフェストが正しくなかったからではありません。マニフェストを実行するための政権運営体制を、旧政権下から大きく変えることができなかったからです。「政治を国民の手に取り戻す」ためには、この二年間の反省を踏まえて、民主党らしい「政権運営の型」を作り、規律・規範に基づいた、国民生活のための政治行政を実現しなければならないのです。
国難の時にあたって、400名を超える私たち民主党議員は、傍観者であってはなりません。今なおがれきが残る中、避難所生活を余儀なくされる被災者の皆さん、放射能の影響におびえながら生活する福島県の皆さんの現状に、私たちも大きな責任を負っていることを自覚しなければなりません。だからこそ、党利党略との決別に向けた政治の刷新、民主党政権の出直しのために、全党一丸となって立ち上がるのが私たちに課せられた歴史的使命ではないでしょうか。
私は、三十代前半で当時最年少の上場企業役員として働く機会を持ちました。企業経営では、社内で派閥争いをしていては、士気は上がりません。経営者がパフォーマンスばかりをやっていても、業績は上がりません。リーダーたる経営者は、高い意識を持って誰よりも困難な仕事に率先して取り組み、さらには社員が失敗を恐れずに全力で仕事に取り組める環境を作っていくことこそが最大の使命であるということを学びました。私は、民主党に足りないと指摘されるのはこうした「経営」実践であると思っています。会社の経営経験が、国家の経営に反映されるべき時が来たのではないか、生き馬の目を抜くビジネスの世界で身につけた経験と力が、混沌とした政治状況を収めるのに役立つのではないかと考え始めました。当選回数の少ない私の挑戦は、永田町の常識からは外れているかもしれません。しかし、私は「新しい次代のリーダー」となるべく社会経験を積んできたつもりです。1998年に民主党が結党され、10余年で念願の政権交代を果たしました。会社でいえば、創業から上場に到ったところです。私は、これまでの代表経験者と違い民主党以外の政党に所属したこともなく、生粋の民主党の国会議員として政治活動をして参りました。そんな私は、諸先輩方の経験やご見識を最大限に生かし、党内をひとつにまとめて、民主党をそして日本の政治を立て直すことの先頭に立っていきたいと考えています。
私は、絶対に逃げない。私は絶対にぶれない。これが民主党再生の最後のチャンスと思って、この戦後最大の国難に立ち向かうために、すべてを賭けて戦ってまいります。
政権政策
~慈しみの心で分かち合う国へ~
震災、経済危機、そして、地域や貧富の格差。いま人々の心に、不信と不安が渦巻いている。国難に直面した今、国民一丸となって復興に立ち上がれる国を作らなければならない。成長を取り戻し、国民生活を底上げし、格差を縮小し、日本国民がひとつになって、それぞれの役割を果たし、助け合う国をつくる。人に対する尊厳をもって、慈しみの心で、総和としての恵みの豊かさを分かち合う国へ。
1.二つの国家的危機を脱する
【①東日本大震災からの復興、原子力災害の収束】
○復興庁に強大な権限と独自財源を 各省縦割りを超えた強大な権限と独自財源を持った復興庁を年内に設置し、被災地に副大臣・政務官を常駐させる。
○被災地に国家プロジェクト特区 地域分散型の電力供給、省エネ環境住宅、最先端の農業・医療等を世界に先駆けて実現する国家プロジェクト特区を、復興のシンボルとして被災地に設置する。
○原子力災害対策を一元化、世界の英知を結集 原子力災害・放射能被害に対応する組織を一元化、世界の英知をも結集し、国が前面に立って事態の収束を果たす。
○国の責任で原発被害に対処 こどもや健康への影響、汚染がれきや土壌の処理、農林水産物への被害等に、国が最終責任を負い、大胆かつ迅速に対処し、最大の透明性・情報公開で国民のみなさんと国際社会からの信頼を取り戻す
○安易な増税に頼らない復興 1000年に1度の天災から世代を超えて復興するとの観点から、その財源は長期償還の国債や無利子非課税国債等でまかない、安易な増税には頼らない。
【②世界経済危機からの脱却】
○積極財政で経済危機に立ち向かう 平成23年度第3次補正予算と平成24年度予算は、急激な円高・株安や世界経済の不透明感を踏まえ、機動的に積極的な予算編成を実施する。
○大胆な金融緩和でデフレ脱却 長期デフレからの脱却と円高の是正を目指し、3年間の集中デフレ脱却期間を設け、マネーサプライの増加など大胆な金融政策を駆使してマクロ経済政策にあたる。
○経済の司令塔「経済戦略会議」を 主要閣僚、日銀総裁、経済界、労働界、学識者等からなる経済戦略会議を司令塔に、オールジャパンで経済政策の基本戦略を策定する。
○財政再建と社会保障の安定 2010年代半ばまでに経済を安定成長路線に乗せ、自然増収を確保する。その上で、中期かつ複数年を枠組みとする財政再建に着手し、医療、介護、年金等社会保障制度の抜本的見直しを図る。
2.世界の先頭に立つ地域分散型国家へ
○「脱・原発依存」、「国策から国責」へ 原子力発電所の再稼動には、新たな厳格な規制体制の下で安全性を徹底的に確保する。耐用年数の経過した原子炉は段階的に廃炉し、「脱・原発依存」のエネルギー政策へと転換する。再処理方針はまず凍結とし高速増殖炉もんじゅ等の核燃料サイクル政策は抜本的に見直す。
○「生活の安全保障」 地方の活性化に向け、農村の6次産業化、再生可能エネルギーを活用した地域分散型の電力供給等に政策資源を重点投下する。日本の豊かな水、肥沃な土地、そして四季折々降り注ぐ太陽といった固有の資源を最大限活用した「未来型食料・エネルギー供給体制」を作り、そこから新たな環境調和型の産業を生み出し、地域分散・循環型の持続可能な産業を実現する。
○危機管理型「首都機能強化」と危機管理本部 危機対応のための専門組織となる危機管理本部(仮称)の整備、首都機能を強化し国家としてのサバイバル機能を強化する。また、首都機能バックアップ都市の整備を図る。
○日米同盟基軸にアジアの安全確保 日米同盟を基軸とし、新たなアジアの安全保障リスクに対応できる安全保障体制を構築する。海上警察権の見直し等により様々な事態に毅然と対応できる体制を整備する。
○経済重視の実利外交 米国、ヨーロッパとのバランスを取った経済連携を行うとともに、中国・韓国・ASEAN・インド等の成長を取り込むことが可能となるアジア中心の経済連携協定の締結を促進、人的交流を深めるなど、現実主義に基づいた実利外交を展開する。
○中長期ビジョンとしての「ひとづくり」「ものづくり」「くにづくり」 技術、環境、教育、観光等を、ニッポン復興の中長期の基幹として位置づける
3.「ねじれ国会」を超えるための国家のガバナンス強化
○ねばり強い国会運営 「大連立」について選択肢を排除するものではないが、現在の政権の枠組みを維持することを前提として、立法府たる国会において政策本位の丁寧な政党間協議を積み重ねる現実的対応を忍耐強く続けることから逃げない。
○政治主導確立のための機能強化 「国家戦略スタッフ」「政務スタッフ」として国会議員、官民の優秀な人材を政治任用する。これにより、政権交代当初に企図していた国家戦略局、行政刷新会議等内閣周辺組織の機能強化を図る。
○政府と党の連携 各省の政務官の一人は国会との連絡調整に専念するものとし、党国対・政調とともに与野党間協議を行う。
○議員立法の充実、政調での法案修正 政調の各部門会議では、野党とも協議しながら積極的な議員立法の作成、政府提出の法案の修正を行うこととし、役所からの報告や勉強の場に加えて、国会対応と一体となった緊張感のある実質審議の場へと役割を強化する。
○党の機能を強化、国の「営業本部」に 政調、国対を束ねる党執行部と官邸・政府の連携を緻密に行い、党執行部は会社で言えば「営業本部」として、一方で国民各層の意見を幅広く吸い上げ、また一方で政府の活動を報告し、各党との調整協議を行うなど対外関係を取り仕切る双方向型組織として機能強化する。
○郵政改革法案の成立 与党3党の最重点合意事項であることはもとより、現在の4分社化では、国民共有の財産である郵便局ネットワークが崩壊してしまう。国会対策上のあらゆる手段を講じることによって、臨時国会で成立させる。